イタチによる庭の植物被害とは?【球根や果実が標的に】被害を最小限に抑える3つの方法

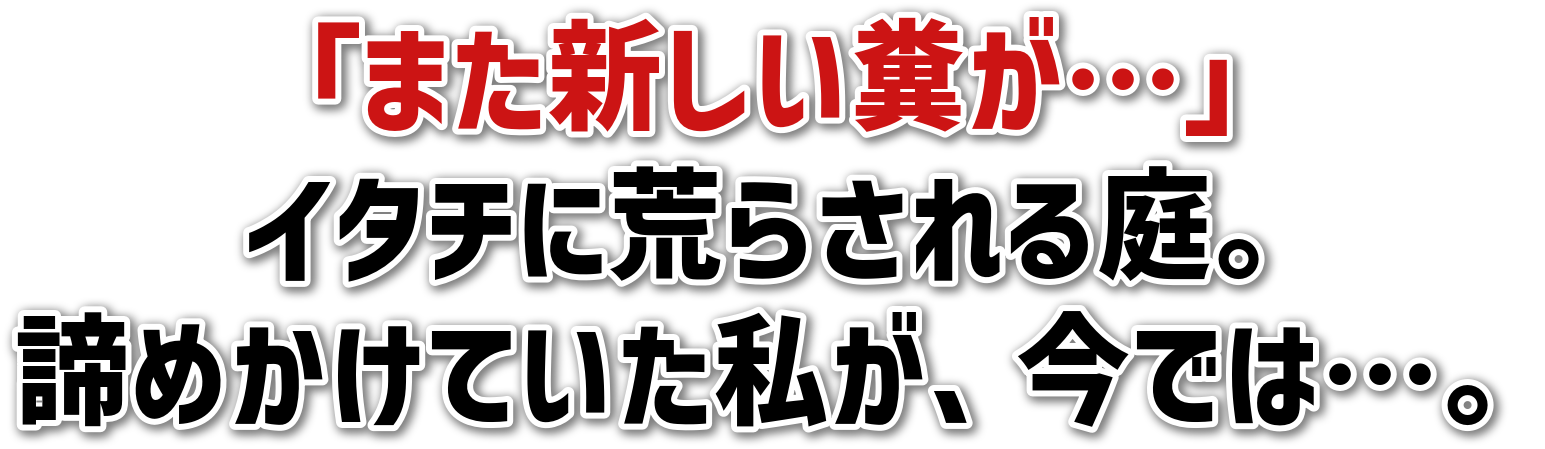
【この記事に書かれてあること】
庭に植えた大切な植物が、イタチにより次々と被害を受けていませんか?- イタチは球根類や低い位置の果実を特に好む
- 被害は季節によって変化し、一晩で庭全体に及ぶことも
- イタチの被害は他の小動物と比べて発見しやすい
- 古いCDやコーヒー粕など身近なもので効果的な対策が可能
- 人の髪の毛やアンモニア水を使った意外な撃退法も
実は、イタチは庭の植物を好んで食べる習性があるんです。
球根や果実が格好の標的となり、一晩で庭全体が荒らされることも。
でも、大丈夫。
身近なものを使った驚きの対策法で、イタチから庭を守ることができます。
この記事では、イタチによる植物被害の特徴と、5つの効果的な対策法をご紹介します。
あなたの庭を守る秘訣がきっと見つかるはずです。
【もくじ】
イタチによる庭の植物被害の実態と特徴

イタチが好む庭の植物「狙われやすい3つ」の特徴
イタチは特に球根類、果実、野菜を好んで狙います。これらの植物が庭にあると要注意です。
イタチの鋭い嗅覚と小回りの利く身体能力のせいで、庭の植物は思わぬ被害を受けることがあります。
「えっ、うちの庭にイタチが来るの?」と思う方もいるかもしれませんが、実は身近な問題なんです。
イタチが特に好む植物には、次の3つの特徴があります。
- 栄養価が高い
- アクセスしやすい場所にある
- 柔らかく食べやすい
「まるで宝探しゲームみたい!」とイタチは喜んでいるかもしれません。
果実では、イチゴやトマトなどの低い位置になる実が狙われやすいです。
イタチは「おいしそう〜」と思いながら、ちょこまかと動いて食べてしまうんです。
野菜も栄養価が高いので、イタチの大好物です。
特に柔らかい新芽や若い葉は、イタチにとって「ごちそう」になっちゃいます。
これらの植物がある庭は、イタチにとって「夢の食べ放題ビュッフェ」のようなもの。
気をつけないと、大切に育てた植物が一晩でなくなってしまうかもしれません。
イタチの好みを知って、適切な対策を取ることが大切です。
球根植物が標的に!「地中の栄養価」がイタチを引き寄せる
イタチが球根植物を好む最大の理由は、地中に豊富な栄養が詰まっているからです。この「地下の宝物」がイタチを引き寄せてしまうんです。
球根は植物の成長に必要な栄養をぎゅっと凝縮して蓄えています。
イタチにとっては、まるで「エネルギー補給ステーション」のようなもの。
「ここを掘れば栄養満点の食事にありつける!」とイタチは考えているのかもしれません。
イタチが球根を狙う理由は他にもあります。
- 掘り起こしやすい柔らかい土
- 鋭い嗅覚で簡単に見つけられる
- 地上部分が小さく、隠れながら食べられる
イタチにとっては「ほいっと掘るだけで食べ物ゲット!」という感じです。
さらに、イタチの鼻は非常に敏感。
地中の球根のにおいを嗅ぎ分けて、ピンポイントで掘り起こすことができるんです。
また、球根植物は地上部分が比較的小さいので、イタチは身を隠しながらゆっくり食事を楽しめます。
「誰にも見つからずに、おいしいごはん♪」とイタチは喜んでいるでしょう。
対策としては、球根の周りに鋭利な小石を敷き詰めたり、強い香りのハーブを一緒に植えたりするのが効果的です。
イタチに「ここは危険だぞ!」と思わせることが大切なんです。
果実被害の特徴「低い位置ほど危険」な理由
イタチによる果実被害は、低い位置にある実ほど危険です。これは、イタチの身体的特徴と行動パターンに深く関係しているんです。
イタチは小型で俊敏な動物です。
地面近くを素早く動き回るのが得意で、低い位置にある果実は絶好のターゲットになってしまいます。
「おっ、おいしそうな実があるぞ!」とイタチは目を輝かせるでしょう。
低い位置の果実が狙われやすい理由は他にもあります。
- 隠れながら食べられる
- エネルギー効率が良い
- 落下した果実も食べられる
- アクセスが容易
「誰にも見つからずにいただきま〜す」という感じですね。
また、高い位置まで登る必要がないので、エネルギー効率も良いんです。
さらに、低い位置の果実は落下しやすく、地面に落ちた果実もイタチの格好の餌になります。
「落ちてるなんてラッキー!」とイタチは喜ぶでしょう。
対策としては、果実の周りにネットを張ったり、低い位置の枝を剪定して実を高い位置につけるようにしたりするのが効果的です。
また、落下した果実はすぐに片付けることも大切です。
ただし、イタチは驚くほどの運動能力を持っています。
「高いところなら安全」と油断していると、イタチが木に登って高い位置の果実を狙うこともあるんです。
総合的な対策が必要になりますね。
イタチの植物被害「季節による変化」を把握せよ!
イタチによる植物被害は季節によって大きく変化します。この変化を理解することで、効果的な対策を講じることができるんです。
春から夏にかけては、新芽や果実が主な標的になります。
イタチにとっては「新鮮な食べ物がいっぱい!」という季節です。
一方、秋から冬は地下の球根類が狙われやすくなります。
「地中に栄養たっぷりの食べ物が隠れてる!」とイタチは考えているかもしれません。
季節ごとのイタチの植物被害の特徴は次のとおりです。
- 春:新芽や若葉、早生の果実が標的に
- 夏:果実や野菜が集中的に狙われる
- 秋:落果や残った野菜、遅生の果実が狙われる
- 冬:地下の球根類や越冬野菜が主な標的に
柔らかい新芽や若葉はイタチにとって「春の味覚」です。
夏になると果実や野菜が豊富になり、イタチにとっては「食べ放題の季節」になってしまいます。
秋は収穫の時期ですが、イタチも負けじと「収穫」を始めます。
落ちた果実や残った野菜を狙います。
冬は地上の食べ物が少なくなるので、イタチは地下の球根類を掘り起こして食べるようになります。
「寒いけど、頑張って掘れば美味しいものが食べられる!」とイタチは考えているでしょう。
この季節変化を把握することで、先手を打った対策が可能になります。
例えば、春には新芽を保護するネットを張り、冬には球根の周りに忌避剤を撒くなど、季節に合わせた対策を講じることが大切です。
イタチの行動を予測して、一歩先を行く対策を心がけましょう。
一晩で全滅も!「イタチの被害規模」を知っておこう
イタチの植物被害は想像以上に深刻で、一晩で庭全体に及ぶことがあります。その被害規模を知ることで、対策の重要性がより明確になるんです。
イタチは小さな体ながら、驚くほどの食欲と行動力を持っています。
一晩で数平方メートルの範囲を荒らすことも珍しくありません。
「今夜はごちそうがいっぱい!」とイタチは大喜びで食べ歩くんです。
イタチの被害規模の特徴は次のとおりです。
- 小規模な家庭菜園なら一晩で全滅の可能性も
- 果樹園では複数の木から実を食べ荒らす
- 球根畑では広範囲に掘り起こし被害が出る
- 野菜畑では様々な種類の野菜を同時に荒らす
- 花壇では花や茎を踏み倒す二次被害も
「小さいからすぐに食べ尽くせる!」とイタチは考えているかもしれません。
一晩で全ての野菜や果実が食べられてしまうことも珍しくありません。
果樹園では、イタチは木から木へと移動しながら実を食べ荒らします。
「あっちの木にも美味しそうな実がなってる!」と、次々と被害を広げていくんです。
球根畑では、イタチが広範囲に渡って地面を掘り起こします。
まるで「宝探しゲーム」をしているかのように、次々と球根を掘り出して食べてしまいます。
野菜畑では、イタチは様々な種類の野菜を同時に荒らします。
「今日はトマト、明日はキュウリ♪」と、まるでビュッフェを楽しむように食べ歩くんです。
花壇の場合、食べる被害だけでなく、イタチが動き回ることで花や茎を踏み倒してしまう二次被害も発生します。
「おっと、ごめんね」なんて言いながら、イタチは構わず動き回るんです。
このような大規模な被害を防ぐためには、早期発見と迅速な対策が不可欠です。
定期的な見回りや、効果的な防御策の導入を心がけましょう。
イタチに「ここは危険だから近づかない方がいい」と思わせることが大切なんです。
イタチvs他の動物!庭の植物被害を比較

イタチと野ウサギ「被害の深刻度」を徹底比較
イタチの植物被害は、野ウサギよりも一般的に深刻です。小回りが利き、多様な植物を攻撃するイタチの方が、被害範囲が広くなりやすいんです。
「えっ、可愛らしいイタチの方が厄介なの?」と思う方もいるかもしれません。
でも、実はそうなんです。
イタチと野ウサギ、どちらが庭にとって厄介な存在なのか、じっくり比べてみましょう。
まず、イタチの特徴をおさらいです。
- 小さな体で素早く動き回る
- 木に登る能力がある
- 地中の球根も掘り起こして食べる
- 果実や野菜など、好む食べ物の種類が多い
- 主に地上の植物を食べる
- 木に登ることはできない
- 好む植物の種類が比較的限られている
地上の野菜から木になる果実、さらには地中の球根まで。
まるで庭全体がビュッフェのような感覚なんでしょうね。
それに比べて野ウサギは「この草が好き」「あの葉っぱが美味しい」といった具合に、好みがはっきりしています。
被害は局所的になりやすいんです。
さらに、イタチは夜行性。
「みんなが寝ている間にこっそり食べよう」という感じで、気づいたときには被害が広がっていることも。
野ウサギは主に朝夕に活動するので、発見しやすく対策も立てやすいんです。
結局のところ、イタチの方が「あっちこっち動き回って、いろんなものを食べちゃう」タイプ。
野ウサギよりも被害が深刻になりやすい、というわけです。
でも、だからこそ対策も重要。
イタチ対策をしっかりすれば、庭を守ることができますよ。
イタチとネズミ「植物被害の発見しやすさ」に違いあり
イタチによる植物被害は、ネズミよりも発見しやすいです。イタチは体が大きく、明確な痕跡を残すため、被害に気づきやすいんです。
「え?小さなネズミの方が見つけにくいの?」と思う方もいるでしょう。
でも、実はそうなんです。
イタチとネズミ、どちらの被害が発見しやすいのか、詳しく見ていきましょう。
まず、イタチの植物被害の特徴をおさらいしてみましょう。
- 体が大きいため、はっきりとした足跡が残る
- 果実や野菜に大きな食べ跡がつく
- 球根を掘り起こした跡が目立つ
- 植物の茎を踏み倒す二次被害もある
- 糞の大きさが5〜8センチと比較的大きい
- 体が小さいため、足跡が見つけにくい
- 果実や野菜に小さな食べ跡がつく
- 地中での活動が多く、地上の痕跡が少ない
- 糞の大きさが1センチ程度と小さい
「ここを通ったぞ」という感じですね。
それに、果実や野菜に大きな食べ跡をつけるので、「あ、これイタチにやられたな」とすぐに分かるんです。
さらに、イタチは球根を掘り起こすのが得意。
まるで「宝探しゲーム」をしているかのように、地面を掘り返します。
その跡は結構目立つんですよ。
一方、ネズミは「こそこそ」と動き回ります。
足跡も小さいので、見逃しやすいんです。
食べ跡も小さいので、気づかないうちに被害が広がっていることも。
「え?いつの間に食べられてたの?」なんてことになりかねません。
糞の大きさも違います。
イタチの糞は「これは何かの糞だな」とすぐに分かる大きさ。
でも、ネズミの糞は小さくて見落としがち。
このように、イタチの被害は「目立つ」んです。
だからこそ、早めの対策が可能になります。
「あ、イタチが来たぞ!」と気づいたら、すぐに対策を始めましょう。
被害を最小限に抑えることができますよ。
イタチとモグラ「地下部分への被害」はどちらが大きい?
植物の地下部分への被害は、モグラの方がイタチよりも大きいです。モグラは完全に地下生活を送り、根や球根を食べ尽くすからです。
「え?イタチよりモグラの方が怖いの?」と驚く方もいるでしょう。
でも、地下部分に限って言えば、本当にそうなんです。
イタチとモグラ、どちらが地下部分に与える被害が大きいのか、詳しく見ていきましょう。
まず、イタチの地下部分への被害の特徴を確認してみましょう。
- 主に球根類を狙う
- 地表から掘り起こして食べる
- 地上部分の被害も同時に起こる
- 季節によって地下部分への被害の程度が変わる
- 根や地下茎を好んで食べる
- 地中を掘り進みながら被害を広げる
- 年中地下で活動し続ける
- 土を掘り返すことで根系を傷つける
確かに被害は出ますが、それほど深くまでは掘りません。
いわば「浅い被害」というわけです。
それに対してモグラは、まるで「地下迷路ゲーム」をしているかのように、どんどん地中を掘り進みます。
「ここにも根っこがある!あっちにも球根がある!」と、次々と食べ進んでいくんです。
さらに、モグラは年中地下で活動し続けます。
「寒いから地上に出るのはやめておこう」なんてことはありません。
四六時中、地下部分を攻撃し続けるんです。
また、モグラは土を掘り返すことで根系を傷つけます。
直接食べなくても、植物にダメージを与えてしまうんです。
「ごめんね、通り道だったから」なんて言いそうですが、植物にとっては大問題。
このように、地下部分に限って言えば、モグラの被害の方が大きいんです。
イタチは地上部分も含めて被害を与えますが、モグラは地下に特化しているため、その部分での被害が甚大になります。
だからといってモグラばかり警戒するのはNG。
イタチ対策もしっかりしましょう。
両方に気を付けることで、庭全体を守ることができますよ。
イタチvs小動物「庭の生態系への影響」を考える
イタチは小動物と比べて、庭の生態系により大きな影響を与える可能性があります。複数の生物種に影響を及ぼし、食物連鎖のバランスを崩す恐れがあるからです。
「えっ、小さなイタチがそんなに影響大きいの?」と思う方もいるでしょう。
でも、実はイタチの存在は庭の生態系に大きな波紋を投げかけるんです。
イタチと他の小動物が庭の生態系に与える影響を、じっくり比べてみましょう。
まず、イタチが庭の生態系に与える影響を見てみましょう。
- 小動物(ネズミ、鳥の卵など)を捕食する
- 果実や野菜、球根など多様な植物を食べる
- 昆虫も捕食対象になる
- 庭を縄張りにして長期滞在する可能性がある
- 主に特定の植物や種子を食べる
- 昆虫を捕食することもある
- 鳥類の餌になることがある
- 季節や環境変化に応じて移動しやすい
小動物を食べたり、果実や野菜をつまんだり、昆虫まで食べちゃったり。
まるで「庭の食べ歩きツアー」をしているみたいですね。
この多様な食性が、生態系に大きな影響を与えるんです。
例えば、イタチがネズミを捕食すると、ネズミの数が減ります。
すると、ネズミが食べていた植物の種が増えすぎたり、逆にネズミを餌にしていた鳥が餌不足になったり。
「ちょっと食べただけなのに」がどんどん連鎖していくんです。
それに、イタチは縄張り意識が強いので、一度庭に住み着くと長期滞在する可能性が高いです。
「ここ、居心地いいな」と思ったら、ずっといるかもしれません。
その間、ずっと生態系に影響を与え続けるわけです。
一方、ネズミなどの小動物は、比較的影響が限定的です。
「この植物が好き」「あの種子が美味しい」といった具合に、食べるものが限られています。
生態系全体を大きく変えるほどの影響力はないんです。
また、小動物は季節や環境の変化に応じて移動しやすいです。
「ここは住みにくくなったな」と思えば、さっさと引っ越してしまいます。
だから、長期的な影響は比較的小さいんです。
このように、イタチは庭の生態系に大きな影響を与える可能性があります。
だからこそ、適切な対策が必要なんです。
イタチと上手く付き合いながら、庭の生態系のバランスを保つことが大切ですよ。
イタチと鳥類「果実被害のパターン」に違いあり!
イタチと鳥類の果実被害パターンには明確な違いがあります。イタチは低い位置の果実を集中的に食べ、鳥類は木の上部の果実を狙う傾向があるんです。
「え?イタチと鳥で食べ方が違うの?」と思う方もいるでしょう。
でも、実はそうなんです。
イタチと鳥類の果実被害パターンの違いを、詳しく見ていきましょう。
まず、イタチの果実被害パターンの特徴を確認してみましょう。
- 低い位置の果実を好んで食べる
- 一度に複数の果実を食べる
- 果実全体をかじる傾向がある
- 地面に落ちた果実も食べる
- 夜間に活動することが多い
- 木の上部や外側の果実を好む
- つつくように一部分を食べることが多い
- 種子を運んで別の場所に落とすことがある
- 主に昼間に活動する
低い位置の果実を集中的に食べます。
まるで「果実ビュッフェ」を楽しんでいるかのようですね。
地面に落ちた果実も「もったいない」と食べてしまいます。
それに、イタチは夜行性。
「みんなが寝ている間にこっそり食べよう」という感じで、夜間に活発に動き回ります。
一方、鳥類は「高いところにある美味しそうな果実を少しずつ」という感じです。
木の上部や外側の果実を狙います。
「ちょっとつついて、美味しいところだけいただこう」という具合ですね。
鳥類は種子を運んで別の場所に落とすことがあります。
「おっと、こぼしちゃった」なんて感じで、知らず知らずのうちに植物の繁殖を手伝っているんです。
また、鳥類は主に昼間に活動します。
「お日様が出ている間に食事しよう」という感じですね。
このように、イタチと鳥類では果実被害のパターンが全然違うんです。
イタチは低い位置の果実を集中的に、鳥類は高い位置の果実を少しずつ。
まるで「分担して食べている」みたいですね。
でも、どちらの被害も農家さんにとっては大問題。
イタチ対策と鳥対策、両方をしっかりすることが大切です。
低い位置にはネットを張り、高い位置には反射テープを付けるなど、それぞれの特徴に合わせた対策が効果的ですよ。
庭を守る!イタチ対策の驚くべき裏技と効果

古いCDで簡単イタチよけ!「反射光」が侵入を防ぐ
古いCDを使ったイタチよけは、意外と効果的な対策方法です。反射光がイタチを怯えさせ、庭への侵入を防ぐんです。
「えっ、CDでイタチが退治できるの?」と思う方もいるでしょう。
でも、これが意外と効くんです。
イタチは光に敏感な動物なんです。
突然の光の動きに驚いて、「ここは危険かも!」と警戒するわけです。
CDを使ったイタチよけの方法は、とっても簡単です。
- 古いCDを集める(5枚以上あるとグッド!
) - CDに穴を開けて、ひもを通す
- 庭の周りの木や柵にCDを吊るす
- 風で揺れるように設置する
この不規則な光の動きが、イタチにとっては「何か危ないものがいる!」と感じさせるんです。
「ぎょっ!何かいる!」とイタチが思って逃げ出すわけです。
この方法のいいところは、環境にやさしくてお財布にも優しいこと。
使わなくなったCDを再利用できますし、新たに何かを買う必要もありません。
「もったいない」精神で、イタチ対策ができちゃうんです。
ただし、注意点もあります。
CDの反射光が近所の方の目に入らないよう、設置場所には気をつけましょう。
「ごめんなさい、イタチよけなんです」と説明するのも恥ずかしいですからね。
また、長期間外に置いておくとCDが劣化する可能性もあります。
定期的に点検して、必要に応じて交換することをおすすめします。
「よしよし、今日もピカピカだな」と、時々チェックしてあげてください。
この方法で、イタチとの知恵比べに勝利しましょう。
きっとイタチも「ここは光るから怖いな」と思って、あなたの庭を避けるようになりますよ。
コーヒー粕でイタチを撃退!「強い香り」が鍵
コーヒー粕を使ったイタチ撃退法は、とても効果的です。強い香りがイタチの嗅覚を惑わせ、植物への接近を妨げるんです。
「えっ、コーヒーの残りカスでイタチが退治できるの?」と驚く方もいるでしょう。
でも、これが意外と効くんです。
イタチは嗅覚が非常に発達した動物。
強い香りは、イタチにとって「ここは危険な場所かも!」というサインになるんです。
コーヒー粕を使ったイタチ対策の方法は、とってもシンプル。
- 使用済みのコーヒー粕を集める
- 天日で乾燥させる(カビ防止のため)
- 庭の周りや植物の根元に撒く
- 雨が降ったら再度撒き直す
「うわっ、この臭いはなに?」とイタチが思って近づかなくなるんです。
さらに、コーヒー粕には肥料効果もあるので、一石二鳥なんです。
この方法の魅力は、エコで経済的なこと。
普段捨ててしまうコーヒー粕を再利用できますし、新たに何かを買う必要もありません。
「もったいない」精神で、イタチ対策と園芸を同時にできちゃうんです。
ただし、注意点もあります。
コーヒー粕を撒きすぎると、土壌が酸性化する可能性があります。
「よーし、たくさん撒いちゃおう!」と思わず張り切りすぎないように気をつけましょう。
また、雨が降るとコーヒー粕が流されてしまうので、定期的に撒き直す必要があります。
「あ、雨が降ったから今日は追加しなきゃ」と、こまめなケアを心がけてください。
この方法で、イタチとの香り勝負に勝ちましょう。
きっとイタチも「ここは変な臭いがするから怖いな」と思って、あなたの庭を避けるようになりますよ。
コーヒーを飲むたびに「ふふふ、これでイタチ対策だ」と思えば、毎日のコーヒータイムがもっと楽しくなるかもしれませんね。
ペットボトルの水で警戒心アップ!「光の反射」を利用
ペットボトルに水を入れて庭に置くと、イタチ対策になります。光の反射と水面の揺らぎがイタチを警戒させ、近づきにくくするんです。
「えっ、ただの水入りペットボトルでイタチが退治できるの?」と思う方もいるでしょう。
でも、これが意外と効果があるんです。
イタチは視覚が敏感な動物。
不規則に動く光や影に対して警戒心を抱くんです。
ペットボトルを使ったイタチ対策の方法は、とってもカンタン。
- 透明なペットボトルを用意する(大きいサイズがおすすめ)
- 水を8分目くらいまで入れる
- 庭の数カ所に設置する
- 定期的に水を入れ替える(藻が生えないように)
風で水面が揺れると、その光の動きが不規則になります。
これがイタチにとっては「何か危ないものがいる!」と感じさせるんです。
「ひえっ、あそこで何か光ってる!」とイタチが思って近づかなくなるわけです。
この方法の魅力は、手軽で低コストなこと。
家にある使用済みペットボトルを再利用できますし、水道水を少し使うだけです。
「もったいない」精神で、イタチ対策ができちゃうんです。
ただし、注意点もあります。
ペットボトルの反射光が近所の方の目に入らないよう、設置場所には気をつけましょう。
「すみません、イタチよけなんです」と説明するのも照れくさいですからね。
また、長期間外に置いておくとペットボトルが劣化したり、水が汚れたりする可能性もあります。
定期的に点検して、必要に応じて交換や水の入れ替えをすることをおすすめします。
「よしよし、今日もキラキラしてるな」と、時々チェックしてあげてください。
この方法で、イタチとの知恵比べに勝利しましょう。
きっとイタチも「ここは何か光るから怖いな」と思って、あなたの庭を避けるようになりますよ。
水を入れるたびに「ふふふ、これでイタチ対策だ」と思えば、庭の手入れがもっと楽しくなるかもしれませんね。
人の髪の毛でイタチを寄せ付けない!「匂いの力」
人の髪の毛を庭に撒くと、イタチを寄せ付けない効果があります。人間の匂いを感じ取ったイタチが警戒し、近づきにくくなるんです。
「えっ、髪の毛でイタチが退治できるの?」と驚く方もいるでしょう。
でも、これが意外と効くんです。
イタチは嗅覚が非常に発達した動物。
人間の匂いは、イタチにとって「ここは危険な場所かも!」というサインになるんです。
髪の毛を使ったイタチ対策の方法は、とってもシンプル。
- 掃除機のゴミや髪のブラシから髪の毛を集める
- 集めた髪の毛を小さな袋に入れる
- 庭の周りや植物の根元に置く
- 定期的に新しい髪の毛に交換する
「うわっ、人間の匂いがする!」とイタチが思って近づかなくなるんです。
さらに、髪の毛は自然に分解されるので、環境にも優しいんです。
この方法の魅力は、コストがかからないこと。
普段捨ててしまう髪の毛を再利用できますし、新たに何かを買う必要もありません。
「もったいない」精神で、イタチ対策ができちゃうんです。
ただし、注意点もあります。
髪の毛を直接地面に撒くと風で飛んでしまう可能性があるので、小さな袋や網に入れるのがおすすめです。
「よーし、髪の毛をバラまいちゃおう!」と思わず張り切りすぎないように気をつけましょう。
また、雨や日光で髪の毛の匂いが薄くなってしまうので、定期的に交換する必要があります。
「あ、今日は髪の毛の交換日だ」と、こまめなケアを心がけてください。
この方法で、イタチとの匂い勝負に勝ちましょう。
きっとイタチも「ここは人間の匂いがするから怖いな」と思って、あなたの庭を避けるようになりますよ。
髪を切るたびに「ふふふ、これでイタチ対策だ」と思えば、散髪も楽しみになるかもしれませんね。
アンモニア水で即効性アップ!「刺激臭」がイタチを遠ざける
アンモニア水を使ったイタチ対策は、即効性があります。強烈な刺激臭がイタチを寄せ付けず、庭から遠ざけるんです。
「えっ、アンモニア水ってあの強烈な臭いのやつ?」と思う方もいるでしょう。
その通りです。
その強烈な臭いこそが、イタチを撃退する武器になるんです。
イタチは嗅覚が非常に発達した動物。
強烈な臭いは、イタチにとって「ここは絶対に危険な場所だ!」というサインになるんです。
アンモニア水を使ったイタチ対策の方法は、こんな感じです。
- アンモニア水を用意する(薬局やホームセンターで購入可能)
- 水で5倍に薄める
- 薄めたアンモニア水を霧吹きに入れる
- 庭の周りや植物の近くの地面に吹きかける
- 雨が降ったら再度吹きかける
「うっ!この臭いはたまらん!」とイタチが思って逃げ出すんです。
効果は即効性があり、短時間でイタチを追い払うことができます。
この方法の魅力は、効果が高いこと。
他の方法で効果が見られない場合でも、アンモニア水なら即座にイタチを遠ざけることができます。
「もう困ったときの最終手段だ!」という感じですね。
ただし、注意点もたくさんあります。
まず、アンモニア水は強烈な臭いがするので、使用時は必ずマスクと手袋を着用してください。
「うわっ、鼻が曲がりそう!」なんてことにならないよう、安全第一で使いましょう。
また、アンモニア水は植物にも影響を与える可能性があるので、直接植物にかけないよう注意が必要です。
「よーし、たっぷりかけちゃおう!」と思わず張り切りすぎないように気をつけましょう。
さらに、子どもやペットがいる家庭では使用を控えた方が良いでしょう。
「あれ?何か変な臭いがする」と近づいてきて危険な目に遭うかもしれません。
この方法は、他の方法が効かなかった場合の「最終兵器」として使うのがおすすめです。
イタチも「ここはあの恐ろしい臭いがするところだ!」と記憶して、長期間寄り付かなくなるでしょう。
ただし、使用する際は周囲への配慮を忘れずに。
近所の方に「すみません、イタチ対策なんです」と説明する羽目にならないよう、風向きや時間帯にも注意しましょう。
アンモニア水を使うときは、責任を持って慎重に扱うことが大切です。
効果は抜群ですが、使い方を誤ると問題を引き起こす可能性もあるので、十分に気をつけて使用してくださいね。