イタチの食性の季節変化は?【夏は果物、冬は小動物中心】年間を通じた被害対策のポイント

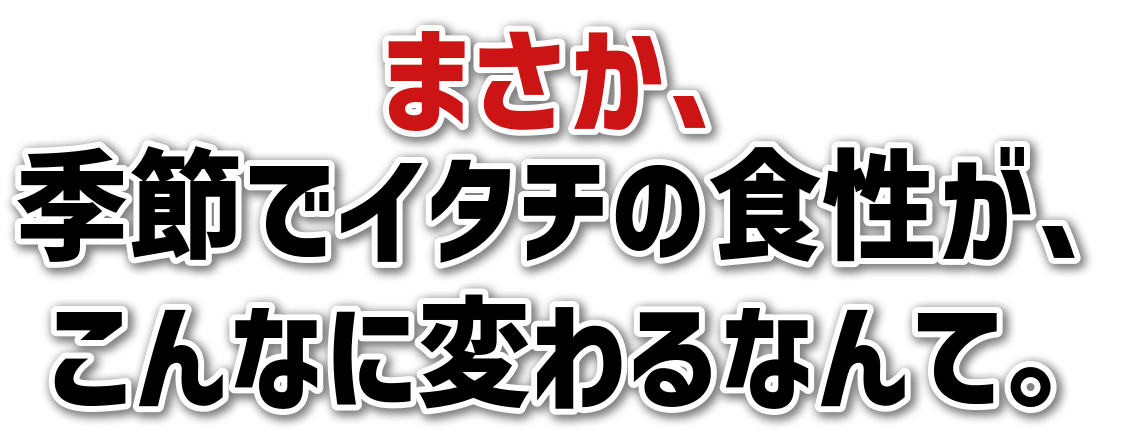
【この記事に書かれてあること】
イタチの食性、季節によって驚くほど変わるんです!- イタチの食性が季節によって大きく変化する
- 夏は果物中心、冬は小動物中心の食生活
- 季節ごとに被害パターンが異なるため注意が必要
- 年間を通じて同じ対策は効果が薄い
- 季節に合わせた5つの驚くべき対策法を紹介
夏は果物党、冬は小動物ハンター。
そんなイタチの変化を知らずに対策していませんか?
季節外れの対策は逆効果になることも。
でも大丈夫。
この記事では、イタチの食性の季節変化を詳しく解説し、それぞれの季節に合わせた効果的な対策法を5つご紹介します。
スイカの皮や猫砂など、意外な方法にビックリするかも。
さあ、イタチとの知恵比べ、始めましょう!
【もくじ】
イタチの食性と季節変化の関係

夏のイタチは「果物党」!甘い誘惑に注意
夏のイタチは果物が大好き!ガブリと甘い果実に食らいつきます。
暑い季節、イタチたちは水分と糖分たっぷりの果物を求めてやってきます。
「あっ、せっかく育てたスイカが!」なんて悲鳴が聞こえてきそうです。
イタチの夏の食生活は、まるで果物パーティー。
庭や果樹園が大好物の宝庫になっちゃうんです。
特に人気なのは:
- みずみずしいスイカ
- 甘酸っぱいイチゴ
- ジューシーなモモ
- 香り豊かなメロン
実は、イタチにとって果物は最高の水分補給源なんです。
ジュワッと果汁が口の中に広がれば、暑さも吹き飛びます。
さらに、果物に含まれる糖分はエネルギー源として最適。
夏の暑さで体力を消耗しがちなイタチにとって、甘い果実は魅力たっぷりなんです。
「でも、うちの庭にはそんな立派な果物ないよ」なんて油断は禁物。
トマトやキュウリだって、イタチには立派なごちそう。
野菜の食害も増えるので要注意です。
夏のイタチ対策は、まさに「果物防衛戦」。
ネットや囲いで守るのはもちろん、完熟前の収穫も効果的。
イタチの「甘い誘惑」から大切な収穫物を守りましょう!
冬のイタチは「小動物ハンター」に変身!
冬が来ると、イタチは一気に肉食系に変身!小動物を追いかけ回す、まさに「ハンター」になります。
「夏はあんなに果物好きだったのに…」なんて驚くかもしれません。
でも、これがイタチの冬の姿なんです。
寒い季節、イタチの狙いは主に:
- チュウチュウとネズミ
- ピョンピョンとウサギ
- コッコッとニワトリ
- チュンチュンと小鳥
それは冬を乗り切るための生存戦略なんです。
冬のイタチは、体温維持のためにたくさんのタンパク質とエネルギーが必要。
果物だけじゃ足りません。
小動物の肉は栄養価が高く、寒さ対策にぴったり。
まるで、私たちが寒い日に熱々の肉料理を食べたくなるのと同じですね。
「イタチさん、うちの鶏舎に来ないでよ〜」なんて心配な声が聞こえてきそう。
実際、冬は鶏舎や小動物の飼育場所での被害が増えます。
イタチにとって、そこは立派な「レストラン」同然。
冬のイタチ対策は「小動物防衛戦」。
鶏舎や飼育場所の補強が重要です。
隙間をしっかり塞いで、イタチの侵入を防ぎましょう。
餌場になりそうな場所の整理整頓も忘れずに。
イタチの食性変化を知れば、季節に合わせた対策ができます。
冬は特に警戒を怠らず、大切なペットや家畜を守りましょう!
春と秋は「オールラウンダー」!多彩な食性に要注意
春と秋のイタチは、まさに「何でも屋さん」。果物も小動物も、お構いなしにパクパク食べちゃいます。
「夏と冬の中間だから、食べ物も中間?」そう、その通りなんです!
この季節、イタチのメニューは実に多彩:
- 甘酸っぱい果物
- 新鮮な野菜
- ピチピチの小魚
- ぷりぷりの昆虫
- モフモフの小動物
なぜこんなに食べ物の幅が広がるのでしょうか?
それは、季節の変わり目だからこそなんです。
春は冬眠から目覚めた虫たちが活発に。
秋は実りの季節で果物がたくさん。
そして、どちらの季節も小動物たちが活発に動き回ります。
イタチにとっては、まさに「食べ放題」の季節なんです。
この時期のイタチは、栄養バランスを整えるのが上手。
果物で糖分、小動物でタンパク質、といった具合に、バランスよく栄養を摂取します。
「まるで栄養士さんみたい!」なんて感心してしまいますね。
でも、困ったことに、この「何でも食べる」習性が、私たちにとっては頭痛の種。
果樹園も畑も、鶏舎も池も、どこもかしこも要注意です。
春と秋のイタチ対策は「総合的な防衛戦」。
果物や野菜の保護はもちろん、小動物の飼育場所の警戒も必要です。
さらに、昆虫や小魚なども狙われるので、庭全体に目を配る必要がありますね。
イタチの食欲旺盛な春と秋。
油断大敵ですが、しっかり対策すれば被害を最小限に抑えられます。
季節の変わり目、イタチ対策もがんばりましょう!
イタチの食性変化を無視すると「被害拡大」の危険性大!
イタチの食性変化を知らないと、大変なことになっちゃいます!季節ごとの対策を怠ると、被害が雪だるま式に大きくなる可能性が。
「えっ、そんなに深刻なの?」って思いますよね。
実は、かなり厄介な事態になりかねないんです。
イタチの食性変化を無視し続けると:
- 夏は果樹園が丸坊主に
- 冬は鶏舎が悲惨な状況に
- 春秋は庭全体が荒らされる
- 一年中、被害が絶えない
夏に果物の対策をしないと、せっかく育てた果実が次々と食べられてしまいます。
「今年の収穫ゼロ…」なんて悲しい結果に。
冬に小動物の保護を怠ると、大切に育てていた鶏や兎が次々と襲われる可能性が。
「朝起きたら鶏舎が…」なんて悲劇が起きかねません。
春と秋は特に要注意。
果物も小動物も狙われるので、対策を怠ると庭全体が荒らされる恐れが。
「庭がぐちゃぐちゃ…」なんてことになりかねません。
こうした被害が積み重なると、経済的にも精神的にも大きな負担に。
家族の楽しみや副収入が失われ、ストレスも溜まります。
最悪の場合、「イタチの被害に耐えられない…」と引っ越しを考えざるを得なくなることも。
でも、安心してください!
イタチの食性変化を理解し、季節に合わせた対策を取れば、被害を最小限に抑えられます。
知識は力なんです。
イタチの習性を知り、季節ごとの対策を立てることで、平和な生活を取り戻せます。
「よし、今年こそイタチに負けない!」そんな気持ちで、しっかり対策を立てていきましょう。
1年中同じ対策は「逆効果」!季節別アプローチが必須
イタチ対策、通年で同じことをしていませんか?それ、実は逆効果かもしれません!
季節によってイタチの好みが変わるので、対策も変える必要があるんです。
「えっ、そんなに細かく対応しなきゃダメ?」って思いますよね。
でも、これが効果的な対策の秘訣なんです。
季節を無視した対策の問題点:
- 夏に冬用の罠を仕掛けても効果ゼロ
- 冬に果物の防護をしても意味なし
- 春秋に偏った対策では半分しか守れない
- イタチを引き寄せてしまう危険性も
「せっかく仕掛けたのに…」なんてガッカリすることに。
逆に、冬に果樹園の防護に力を入れても、小動物を狙う冬のイタチには全く効果がありません。
「果物は守れたけど、鶏舎が…」なんて悲しい結果に。
さらに怖いのは、季節外れの餌をうっかり置いてしまうこと。
例えば、冬に熟した果物を庭に放置すると、かえってイタチを引き寄せてしまう可能性が。
「対策したのにイタチが来た!」なんて逆効果になっちゃいます。
では、どうすればいいの?
答えは季節別のアプローチです!
- 夏:果樹園や菜園の防護に重点を
- 冬:小動物の保護と隙間封鎖を徹底
- 春秋:果物と小動物、両方をカバー
「よし、これでイタチに勝てる!」そんな自信が湧いてきますね。
季節を考慮したイタチ対策、少し手間はかかりますが、確実に効果は上がります。
イタチとの知恵比べ、季節の変化を味方につけて勝利を掴みましょう!
季節で変わるイタチの被害パターンと対策法

夏の果樹園vs冬の鶏舎!被害の違いを比較
夏と冬では、イタチの被害パターンが大きく変わります。夏は果樹園が狙われ、冬は鶏舎が危険にさらされるんです。
夏のイタチ被害といえば、果樹園が標的になっちゃいます。
「あれ?昨日まであったスイカが…」なんて悲しい経験をした人もいるかもしれません。
イタチは甘くて水分たっぷりの果物が大好物。
特に注意が必要なのは:
- スイカやメロンなどの大型果物
- イチゴやブドウなどの小粒果実
- モモやスモモなどの柔らかい果物
- トマトやキュウリなどの野菜果実
高い場所にある果実も簡単に狙われちゃうんです。
一方、冬になると被害の舞台は一変。
今度は鶏舎や小動物の飼育場所が危険にさらされます。
「コケコッコー」という鳴き声が聞こえなくなったら要注意です。
冬のイタチは、タンパク質とエネルギーを求めて小動物を狙います。
- ニワトリやウズラなどの家禽類
- ウサギやモルモットなどのペット
- 飼育中の観賞魚
実は、イタチの食性が季節によって大きく変わるからなんです。
夏は水分と糖分、冬はタンパク質とエネルギー。
イタチの季節ごとの栄養ニーズに合わせて、被害パターンも変化するというわけ。
だから、季節に応じた対策が必要になります。
夏は果樹園の防衛、冬は小動物の保護に重点を置くのがポイント。
イタチの習性を知って、季節別の対策を立てれば、年中安心して暮らせるはずです。
春秋の「二刀流被害」にどう立ち向かう?
春と秋は、イタチの食性が「二刀流」になる時期。果物も小動物も両方狙われるので、対策が難しくなります。
でも、大丈夫。
しっかり準備すれば、この厄介な時期も乗り越えられます。
春秋のイタチは、まるで「何でも屋さん」。
果物パクパク、小動物ガブリ。
「どっちを守ればいいの?」って混乱しちゃいますよね。
実は、両方守る必要があるんです。
春秋に注意すべきポイントは:
- 果樹園や菜園の新芽や若葉
- 早生の果物や遅生の果物
- 小動物の赤ちゃん
- 活発に動き回る昆虫類
果物でビタミン補給、小動物でタンパク質チャージ。
まるで栄養士さんみたいですね。
でも、そんなイタチの「二刀流」にも対抗策はあります。
- 複合的な防護策:果樹園にネットを張りつつ、小動物の飼育場所も補強。
- こまめな見回り:朝晩の点検で、被害の早期発見を。
- 臭いを利用した対策:ニンニクやハーブのスプレーで、果樹園と鶏舎の両方を守る。
- 環境整備:庭や畑の整理整頓で、イタチの隠れ場所をなくす。
でも、安心してください。
これらの対策は、少しずつ習慣にしていけばOK。
春秋の「二刀流被害」は確かに厄介。
でも、私たちも「二刀流対策」で立ち向かえば大丈夫。
果物も小動物も、しっかり守り抜きましょう。
この時期を乗り越えれば、イタチ対策マスターの称号をゲットできるはずです!
夏は「防護ネット」冬は「隙間封鎖」!季節別ベスト対策
季節によってイタチの行動が変わるなら、対策も季節に合わせて変えなきゃ。夏は「防護ネット」で果物を守り、冬は「隙間封鎖」で小動物を守る。
これが季節別ベスト対策なんです。
まず夏の対策。
キーワードは「防護ネット」です。
- 果樹園全体をネットで覆う:目の細かいネットを選んでね。
- 個別の果実を袋で保護:特に大切な果実は個別ガード。
- 地面近くのネットを固定:イタチは下からも侵入するよ。
- ネットの定期点検:破れや隙間がないか、こまめにチェック。
でも、一度設置すれば長期間使えるんです。
果物を守る頼もしい味方になってくれますよ。
次は冬の対策。
ここでのキーワードは「隙間封鎖」。
- 鶏舎や小屋の隙間をふさぐ:5mm以上の隙間は要注意。
- 扉や窓の締まりを確認:閉め忘れに気をつけて。
- 床下や屋根裏の点検:侵入されやすい場所をガード。
- 配管周りの隙間も忘れずに:小さな穴もイタチには十分。
でも、イタチは本当に小さな隙間から入り込んでくるんです。
油断大敵ですよ。
そして、忘れちゃいけないのが通年対策。
- 餌場をなくす:生ゴミの管理を徹底。
- 庭の整理整頓:隠れ場所をつくらない。
- 忌避剤の利用:天然成分のものがおすすめ。
「よし、今年こそイタチに負けない!」って気持ちで、しっかり対策を立てていきましょう。
季節の変化を味方につければ、イタチ対策もばっちりです!
イタチの捕食量は夏と冬で大違い!
イタチの食欲、実は季節によってかなり変わるんです。夏と冬では、捕食量に大きな差が。
この違いを知れば、対策も的確になります。
まず、衝撃の事実。
冬のイタチは、夏の約1.5倍も食べるんです!
「えっ、寒い冬の方が食欲旺盛なの?」って思いますよね。
実はこれ、冬を乗り切るための生存戦略なんです。
夏と冬の捕食量の違い:
- 夏:体重の約15%(1日)
- 冬:体重の約20〜25%(1日)
これ、人間に例えると、夏はおにぎり5個、冬はおにぎり7〜8個を毎日食べるようなもの。
すごい食欲ですよね。
でも、単に量が違うだけじゃないんです。
捕食の頻度も変わります。
- 夏:1日4〜5回
- 冬:1日2〜3回
冬はガッツリ食べる「大食派」といった感じです。
じゃあ、具体的に何を食べるの?
ここでも季節差が出ます。
- 夏の主食:果物(スイカ1/4個分≒ネズミ1匹分)
- 冬の主食:小動物(ネズミ2〜3匹/日)
実は、スイカの甘い香りがイタチを誘っているんです。
この捕食量の違い、対策にどう活かせばいいの?
- 夏:こまめな果実の収穫が効果的
- 冬:小動物の保護強化が重要
冬は鶏舎などの防御を念入りに。
こうすれば、イタチの季節ごとの食欲に合わせた対策ができます。
イタチの食欲、侮れません。
でも、この季節変化を知っておけば、効果的な対策が立てられるはず。
「さあ、イタチの食欲に負けないぞ!」って気持ちで、しっかり準備していきましょう。
季節変化を逆手に取る!イタチの習性を利用した撃退法
イタチの季節による習性の変化、実はこれ、私たちの味方にもなるんです。イタチの特徴を逆手に取れば、効果的な撃退が可能になります。
さあ、イタチの習性を利用した驚きの撃退法、ご紹介しましょう。
まず押さえておきたいのが、イタチの季節ごとの特徴。
- 夏:果物好き、暑さに弱い
- 冬:小動物好き、寒さに強い
- 春秋:何でも食べる、活動的
夏の撃退法:
- 氷入りペットボトルの設置:暑がりのイタチは冷たい場所を避けます。
- スイカの皮の活用:強烈な匂いでイタチを混乱させます。
- 扇風機の風:涼しい風が苦手なイタチを寄せ付けません。
実は、イタチは意外と繊細な生き物なんです。
冬の撃退法:
- 使用済み猫砂の利用:天敵の匂いでイタチを警戒させます。
- 唐辛子パウダーの散布:刺激臭がイタチを遠ざけます。
- 人工的な光や音:冬の静寂を破る光や音に敏感です。
イタチの鋭い嗅覚を逆手に取る作戦なんです。
春秋の撃退法:
- ニンニク&ハーブスプレー:強い香りで全方位的に防御します。
- 風車の設置:動きと音でイタチを威嚇します。
- コーヒーかすの活用:強い香りで侵入を防ぎます。
身近なものでも、使い方次第で強力な味方になるんです。
そして、一年中使える方法もあります。
- 古いCDの利用:反射光がイタチを怖がらせます。
- ペットボトル風車:音と動きで警戒心を煽ります。
- 竹串やつまようじの配置:鋭利な物が苦手なイタチを寄せ付けません。
でも、イタチの習性を知れば、意外なものが強力な武器になるんです。
イタチの季節による変化を逆手に取れば、効果的な対策が可能になります。
自然の摂理に逆らわず、うまく利用する。
そんな知恵を働かせれば、イタチとの共存も夢じゃありません。
「よーし、これでイタチ対策バッチリ!」って自信が湧いてきませんか?
季節の変化を味方につければ、イタチ撃退も楽しくなるはずです。
さあ、イタチとの知恵比べ、楽しんでいきましょう!
イタチの食性変化を知って快適な生活を取り戻す

夏はスイカの皮でイタチを撃退!意外な活用法
夏のイタチ対策に、スイカの皮が大活躍!意外ですが、これが効果抜群なんです。
「え?スイカの皮でイタチが退治できるの?」って思いますよね。
実は、スイカの強烈な香りがイタチを混乱させるんです。
イタチにとっては、まるで迷路に迷い込んだような感覚になっちゃうんです。
スイカの皮の活用法、こんな感じです:
- 食べ終わったスイカの皮を2〜3cm幅に切る
- イタチの通り道や侵入しそうな場所に置く
- 2〜3日おきに新しい皮に取り替える
- 効果が薄れてきたら、場所を変えてみる
大丈夫です。
数日で取り替えれば問題ありません。
むしろ、少し発酵した方が香りが強くなって効果的なんです。
この方法のすごいところは、イタチを傷つけずに追い払えること。
イタチだって生きものです。
優しく対処できるのが魅力ですね。
それに、夏の暑い時期は特に効果的。
なぜって?
イタチは暑さに弱いんです。
スイカの香りで混乱し、さらに暑さでグッタリ。
「もう、この家には近づかない!」ってなっちゃうわけです。
ただし、注意点も。
スイカの皮を置いたら、他の動物が寄ってくる可能性もあります。
特に、アリなどの虫には要注意。
でも、定期的に取り替えれば大丈夫。
「よーし、今年の夏はスイカでイタチ退治だ!」って感じで、ぜひ試してみてください。
夏の楽しみが、イタチ対策にもなるなんて、一石二鳥ですよね。
さあ、スイカを食べながら、イタチ対策を楽しみましょう!
冬は使用済み猫砂でイタチを寄せ付けない!
冬のイタチ対策に、意外な強い味方が!それは、なんと使用済みの猫砂なんです。
驚きですよね。
「え?汚い猫砂を庭に撒くの?」って思うかもしれません。
でも、これがイタチを寄せ付けない秘密兵器なんです。
なぜって?
イタチにとって、猫は天敵の一つ。
その匂いを嗅ぐだけで、ビクビクしちゃうんです。
使用済み猫砂の活用法はこんな感じ:
- 使用済み猫砂を小さな布袋に入れる
- イタチの侵入しそうな場所に置く
- 1週間ごとに新しいものと交換
- 雨に濡れないよう、屋根のある場所がおすすめ
大丈夫です。
人間には、そこまで強い匂いは感じません。
でも、鋭い嗅覚を持つイタチには、強烈な警告信号になるんです。
この方法の良いところは、環境にやさしいこと。
化学物質を使わずに、自然な方法でイタチを遠ざけられます。
しかも、捨てるはずだった猫砂が再利用できるなんて、エコですよね。
冬は特に効果的です。
なぜかって?
冬のイタチは小動物を狙います。
でも、猫の匂いがする場所には、小動物も寄り付きません。
つまり、イタチの食事場所を奪っちゃうんです。
「ここには餌がないぞ」って、イタチが勝手に思い込んでくれるわけ。
ただし、注意点も。
猫を飼っていない家庭では、ご近所や友人から分けてもらう必要があります。
「イタチ対策に使うから、使用済み猫砂ちょうだい」なんて、ちょっと面白い会話になりそうですね。
「よし、今年の冬はこれでイタチ対策だ!」って感じで、ぜひ試してみてください。
意外な方法ですが、効果は抜群。
イタチとの知恵比べ、楽しんでいきましょう!
春秋はニンニク&ハーブスプレーが効果的!
春と秋のイタチ対策に、強い味方が登場!それは、ニンニクとハーブを混ぜた手作りスプレーなんです。
香り高い天然の忌避剤、すごいでしょ?
「え?ニンニク臭くない?」って思いますよね。
でも大丈夫。
ハーブの香りで、そんなに気にならないんです。
それに、この組み合わせがイタチには効果抜群なんです。
作り方と使い方はこんな感じ:
- ニンニク2片をすりおろす
- 好みのハーブ(ミント、ローズマリーなど)を刻む
- 水1リットルに材料を入れて一晩置く
- こして、スプレーボトルに入れる
- イタチの通り道や侵入しそうな場所に吹きかける
1週間に2〜3回くらいがおすすめ。
雨が降ったら、すぐに吹きかけ直すのがコツです。
この方法の良いところは、安全で自然なこと。
化学薬品じゃないから、子どもやペットがいる家庭でも安心して使えます。
しかも、材料は台所にあるものばかり。
経済的ですよね。
春と秋に特に効果的な理由は、イタチの食性にあるんです。
この季節、イタチは果物も小動物も狙います。
つまり、庭全体が餌場になっちゃうんです。
でも、このスプレーを使えば、庭全体をガードできるんです。
ただし、注意点も。
ハーブの種類によっては、植物に影響が出ることも。
心配な場合は、植物から少し離れた場所に吹きかけてくださいね。
「よーし、今年の春秋はこれでイタチ撃退だ!」って感じで、ぜひ試してみてください。
自然の力を借りたイタチ対策、素敵じゃないですか?
さあ、香り高い庭で、イタチフリーの季節を楽しみましょう!
1年中使える!CDの反射光でイタチを怖がらせる
年中使えるイタチ対策、見つけました!それは、なんと古いCDを使った反射光作戦なんです。
意外でしょ?
「え?CDでイタチが退治できるの?」って思いますよね。
実は、CDの反射光がイタチを怖がらせるんです。
キラキラ光る不思議な物体に、イタチはビビっちゃうんです。
CDの活用法、こんな感じです:
- 使わなくなったCDを用意する
- CDに穴を開けて、ひもを通す
- イタチの通り道や侵入しそうな場所に吊るす
- 風で揺れるように設置する
- 複数のCDを使って、広範囲をカバー
確かに、ちょっと変わった庭の飾りになりますが、工夫次第でおしゃれにも見えるんです。
むしろ、キラキラ光るモビールみたいで素敵かも?
この方法のすごいところは、一年中効果があること。
季節を問わず、イタチを寄せ付けません。
しかも、メンテナンスもほとんど不要。
時々、ホコリを拭くくらいでOKなんです。
それに、コストもかからないのが魅力。
捨てるはずだったCDが、立派なイタチ対策グッズに大変身。
「もったいない精神」にもぴったりですね。
ただし、注意点も。
強い日差しの下では、反射光が強すぎることも。
neighbors*への配慮を忘れずに。
また、風の強い日は、CDが飛ばされないよう、しっかり固定してくださいね。
「よし、今日からCDでイタチ対策開始だ!」って感じで、ぜひ試してみてください。
イタチ対策が、ちょっとしたアート作品づくりになるなんて、面白いですよね。
さあ、キラキラ光る庭で、イタチフリーの日々を楽しみましょう!
換気扇近くにコーヒーかす!香りで侵入を防ぐ
意外なイタチ対策、見つけました!それは、なんとコーヒーかすを使った香り作戦なんです。
驚きですよね。
「え?コーヒーかすでイタチが来なくなるの?」って思うでしょう。
実は、コーヒーの強い香りがイタチを混乱させるんです。
人間には良い香りでも、イタチには「ここは危険!」って感じる匂いなんです。
コーヒーかすの活用法、こんな感じ:
- 使用済みのコーヒーかすを乾燥させる
- 小さな布袋や網袋に入れる
- 換気扇の近くや窓際に置く
- 2週間ごとに新しいものと交換
- 雨に濡れないよう、屋内側に設置
大丈夫です。
乾燥させたコーヒーかすは、そこまで強い匂いは出しません。
むしろ、ほんのりコーヒーの香りがして、心地よいくらいなんです。
この方法の良いところは、環境にやさしく経済的なこと。
捨てるはずだったコーヒーかすが再利用できるなんて、エコですよね。
しかも、お金もかからない。
一石二鳥どころか、三鳥くらいの価値があります。
換気扇の近くに置くのがポイント。
なぜって?
イタチは換気扇の隙間から侵入しようとすることが多いんです。
その入り口で「ストップ!」をかけられるわけです。
ただし、注意点も。
コーヒーかすは湿気を吸いやすいので、カビに注意。
定期的な交換を忘れずに。
また、他の動物(特に猫)が気になる可能性もあるので、置き場所には気をつけてくださいね。
「よーし、今日からコーヒーでイタチ対策だ!」って感じで、ぜひ試してみてください。
朝のコーヒータイムが、イタチ対策にもなるなんて、素敵じゃないですか?
さあ、香り高い家で、イタチフリーの生活を楽しみましょう!