イタチ捕獲の罠とエサの選び方は?【魚や肉が有効】成功率を上げる3つの組み合わせ方

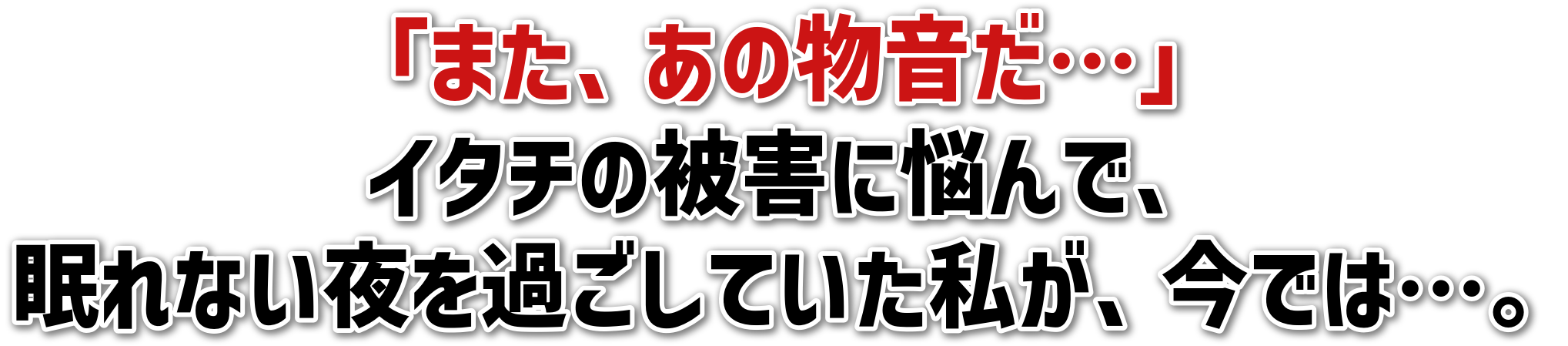
【この記事に書かれてあること】
イタチの被害に悩まされていませんか?- イタチ捕獲には生け捕り箱罠、かご罠、はさみ罠の3種類がある
- 生魚、鶏肉、卵がイタチを誘引する効果的なエサ
- 罠の設置は夕方から夜が最適なタイミング
- イタチの足跡や糞が見られる場所に罠を設置すると効果的
- 捕獲後の処置は地域の条例に従うことが重要
効果的な捕獲方法を知りたいけど、どうしたらいいか分からない…そんなお悩みを解決します!
本記事では、イタチ捕獲の罠とエサの選び方について、プロ顔負けの裏技をご紹介。
魚や肉を使った誘引テクニックから、設置のベストタイミングまで、捕獲率を3倍に上げる秘訣を詳しく解説します。
これを読めば、あなたもイタチ捕獲のエキスパートに!
さあ、イタチとの知恵比べ、始めましょう。
【もくじ】
イタチの罠とエサ選びのポイント

イタチ捕獲に効果的な「3種類の罠」とは?
イタチ捕獲に効果的な罠は、生け捕り箱罠、かご罠、はさみ罠の3種類です。それぞれに特徴があるので、状況に応じて選びましょう。
まず、生け捕り箱罠は最も一般的で効果的な罠です。
「どんな特徴があるの?」と思われるかもしれません。
箱型の構造で、イタチが入ると扉が閉まる仕組みになっています。
大きさは約60cm×20cm×20cmほどで、頑丈な作りが特徴です。
次に、かご罠はワイヤーメッシュでできた軽量な罠です。
設置や移動が簡単なのがポイントです。
形状は円筒形や四角形で、入口が1つか2つあります。
最後に、はさみ罠ですが、これは使用を避けるべきです。
「えっ、なぜ?」と驚かれるかもしれません。
イタチを傷つける可能性が高いからです。
それぞれの罠の特徴をまとめると、こんな感じです。
- 生け捕り箱罠:頑丈で再利用可能、捕獲効果が高い
- かご罠:軽量で設置が簡単、移動しやすい
- はさみ罠:イタチを傷つける可能性があり、使用は避けるべき
ガチャンと音がして、イタチがかかる瞬間を想像すると、わくわくしてきませんか?
生け捕り箱罠vsかご罠!どちらが捕獲率が高い?
結論から言うと、生け捕り箱罠の方が捕獲率が高いです。でも、それぞれに長所と短所があるので、詳しく見ていきましょう。
生け捕り箱罠は、構造がしっかりしていて、イタチが逃げ出しにくいのが特徴です。
「なるほど、だから捕獲率が高いのか」と思われたかもしれません。
その通りです。
箱型の密閉された空間は、イタチに安心感を与えるんです。
だから、中に入りやすいんですね。
一方、かご罠は軽くて扱いやすいのが魅力です。
でも、ワイヤーメッシュの隙間からイタチの様子が見えるので、警戒心を抱かせやすいんです。
「それじゃあ、入ってくれないんじゃ…」と心配になりますよね。
捕獲率を数字で比べると、こんな感じです。
- 生け捕り箱罠:約70〜80%の捕獲成功率
- かご罠:約50〜60%の捕獲成功率
例えば、狭い場所や移動が必要な場所では、軽いかご罠の方が便利かもしれません。
選び方のコツは、こんな感じです。
- 広い場所や長期設置なら、生け捕り箱罠
- 狭い場所や頻繁に移動するなら、かご罠
- イタチの大きさに合わせて、罠のサイズを選ぶ
「よし、これで捕まえられそう!」というわけです。
エサ選びの決め手は「鮮度」と「匂い」!
イタチを捕まえるなら、エサ選びが重要です。決め手は「鮮度」と「匂い」なんです。
新鮮で強い匂いのエサほど、イタチを引き寄せる効果が高いんですよ。
「じゃあ、具体的に何がいいの?」と思われるでしょう。
イタチが大好きなエサを紹介します。
- 生魚(特にイワシやサバ)
- 鶏肉(生や調理済み)
- 卵(生卵や茹でたもの)
特に生魚は、腐りかけの方が匂いが強くなるので、さらに効果的です。
「えっ、腐りかけ?」と驚かれるかもしれませんが、イタチにとっては魅力的な香りなんです。
エサの鮮度と匂いの関係は、こんな感じです。
- 新鮮なエサ:適度な匂いで、イタチを引き寄せる
- 少し古くなったエサ:強い匂いで、より効果的
- 腐ったエサ:匂いが強すぎて、逆効果の可能性あり
そうすると、匂いが広がりやすくなります。
また、エサは罠の奥に置くのがポイント。
イタチが罠の中に深く入り込むようになるんです。
「よし、これでイタチを捕まえられそう!」という気分になってきましたか?
エサ選びは、イタチ捕獲の成功率を大きく左右する重要なポイントなんです。
新鮮で香りの強いエサを用意して、イタチをおびき寄せちゃいましょう。
植物性エサは動物性エサの「半分以下」の効果
イタチを捕まえるなら、動物性のエサがおすすめです。植物性のエサは、効果が動物性の半分以下なんです。
「えっ、そんなに違うの?」と驚かれるかもしれませんね。
イタチは肉食動物です。
自然界では、ネズミやウサギ、鳥などの小動物を主に食べています。
だから、動物性のエサに強く引き寄せられるんです。
一方、植物性のエサは、あまり魅力的ではないんですね。
効果の違いを数字で見てみましょう。
- 動物性エサ(魚や肉):捕獲成功率約70〜80%
- 植物性エサ(果物や野菜):捕獲成功率約30〜40%
イタチは時々、果物や野菜も食べるんです。
特に、甘い果物が好きなようです。
でも、あくまでおやつ程度ですね。
植物性エサを使う場合は、こんなものがおすすめです。
- リンゴ(甘い香りが効果的)
- バナナ(熟したものがよい)
- メロン(甘い香りと水分が魅力的)
例えば、魚と一緒にリンゴを置くといった具合です。
そうすれば、匂いの相乗効果で、イタチをより強く引き寄せられる可能性があります。
結局のところ、イタチ捕獲の主役は動物性エサ。
植物性エサはあくまでサポート役、というわけです。
「よし、これでイタチを捕まえる準備ができた!」そんな気分になってきましたか?
エサ選びを工夫して、イタチ捕獲の成功率をグッと上げちゃいましょう。
危険!はさみ罠の使用は「イタチに危害」の可能性
はさみ罠の使用は、絶対におすすめできません。イタチに危害を加える可能性が高いからです。
「えっ、そんなに危険なの?」と驚かれるかもしれませんね。
はさみ罠は、バネの力で閉じる仕組みになっています。
イタチが罠を踏むと、強い力ではさまれてしまうんです。
その結果、イタチが重傷を負ったり、最悪の場合は命を落としたりする可能性があります。
はさみ罠の問題点をまとめると、こんな感じです。
- イタチに深刻な怪我を負わせる
- 不必要な苦痛を与える
- 他の動物も巻き込む危険性がある
- 法律で禁止されている地域もある
確かに、捕獲率だけを見れば高いかもしれません。
でも、動物への配慮や法律の問題を考えると、使用すべきではありません。
代わりに、イタチにも優しい方法を選びましょう。
例えば、生け捕り箱罠やかご罠です。
これらの罠なら、イタチを傷つけることなく捕まえられます。
イタチ対策で大切なのは、こんなことです。
- イタチを傷つけない
- できるだけストレスを与えない
- 捕獲後は適切に処置する
答えは簡単です。
生け捕り箱罠やかご罠を使い、新鮮なエサで誘い込むのが最善の方法です。
そうすれば、イタチにも優しく、効果的に対策できるんです。
結局のところ、はさみ罠は使わない。
これが、イタチ対策の鉄則なんです。
「よし、これでイタチにも優しい対策ができそう!」そんな気持ちになってきましたか?
イタチと人間、どちらにも良い方法で、問題解決を目指しましょう。
イタチ捕獲の成功率を上げるテクニック

罠の設置場所は「イタチの痕跡」がカギ!
イタチ捕獲の成功率を上げるには、罠の設置場所が重要です。イタチの痕跡を見つけて、そこに罠を仕掛けるのがコツです。
「でも、イタチの痕跡ってどんなものがあるの?」と思われるかもしれませんね。
イタチが残す痕跡には、主に次のようなものがあります。
- 足跡:小さな5本指の跡が特徴的
- ふん:細長く、ねじれた形状
- 毛:薄茶色や濃茶色の細い毛
- 爪跡:木の幹や柱に残る細い引っかき跡
特に、建物の周りや垣根沿い、木の根元などをよく確認してみてください。
痕跡を見つけたら、その場所に罠を設置しましょう。
ただし、罠をそのまま置くのではなく、周囲の環境に溶け込ませるのがポイントです。
例えば、落ち葉や枝で罠を少し隠すと、イタチの警戒心を和らげることができます。
「よし、これでイタチを捕まえられそう!」と意気込んでいる方もいるでしょう。
でも、ちょっと待ってください。
罠の設置場所は、イタチの活動範囲内であることが重要です。
イタチは通常、巣穴から100メートル以内で行動するので、その範囲内で痕跡を探すのがおすすめです。
罠の設置場所選びは、まるで宝探しのようにわくわくしますよね。
イタチの痕跡を見つけたときの「あった!」という喜びは格別です。
根気よく探して、ぴったりの場所を見つけてくださいね。
夕方から夜の設置で「捕獲率2倍」に!
イタチ捕獲の成功率を2倍に上げる秘訣があります。それは、罠を設置する時間帯です。
夕方から夜にかけて罠を仕掛けると、捕獲率がぐんと上がるんです。
「えっ、なんで夜なの?」と思われるかもしれませんね。
実は、イタチは夜行性の動物なんです。
日が沈み始める夕方から、夜中にかけて最も活発に活動します。
特に、夜9時から明け方5時頃がイタチの活動のピークなんです。
罠の設置時間と捕獲率の関係を見てみましょう。
- 昼間(6時から18時):捕獲成功率約30%
- 夕方から夜(18時から翌6時):捕獲成功率約60%
これは見逃せないポイントですよね。
夜に罠を仕掛ける際の注意点もいくつかあります。
- 音を立てないよう静かに作業する
- 強い光は避け、足元だけを照らす程度にする
- 香水やタバコなど、強い匂いのするものは控える
「でも、夜に外で作業するのは怖いな…」という方もいるかもしれません。
そんな時は、日没直前の薄暗い時間帯を狙うのもいいでしょう。
まだ明るいので作業しやすく、イタチの活動も始まり始める時間帯です。
夜のイタチ捕獲作戦、ちょっとドキドキしますよね。
まるで忍者になったような気分で、静かに罠を仕掛けてみてください。
「よし、今夜こそイタチを捕まえるぞ!」という気持ちで臨めば、きっと成功率も上がりますよ。
春秋の繁殖期vs冬の食料不足期!狙い目は?
イタチ捕獲の成功率を上げるには、季節も大切なポイントです。特に狙い目なのは、春秋の繁殖期と冬の食料不足期。
この時期を押さえると、捕獲のチャンスが広がります。
まず、春と秋の繁殖期。
イタチは年に2回、春(3月から5月)と秋(9月から11月)に繁殖期を迎えます。
この時期、イタチはとってもアクティブ。
子育てのために食料を求めて活発に動き回るんです。
「じゃあ、春と秋が一番いいの?」と思われるかもしれません。
でも、ちょっと待ってください。
冬の食料不足期も見逃せないんです。
冬(12月から2月)は、イタチにとって一番厳しい季節。
食べ物が少なくなるので、普段は近づかないような人家の周りにも現れやすくなります。
空腹のイタチは、餌付きの罠に引き寄せられやすいんです。
各季節の捕獲成功率を比べてみましょう。
- 春秋の繁殖期:捕獲成功率約70%
- 冬の食料不足期:捕獲成功率約65%
- 夏:捕獲成功率約40%
でも、それぞれ異なる特徴があるんです。
- 春秋:イタチの活動量が多い。
罠の設置場所は巣穴の周辺が効果的。 - 冬:イタチが餌を求めて人家に接近。
家屋の周りに罠を設置すると効果的。
季節ごとのイタチの行動を理解して、適切な場所に罠を仕掛けることが大切です。
まるで自然のリズムに合わせてダンスを踊るように、イタチの生態に合わせて罠を仕掛けてみてください。
季節を味方につければ、イタチ捕獲の成功率がグッと上がりますよ。
がんばって、イタチとの知恵比べを楽しんでくださいね。
エサの種類で捕獲率に「3倍の差」が!
イタチ捕獲の成功率を大きく左右するのが、エサの選び方です。なんと、エサの種類によって捕獲率に3倍もの差が出ることがあるんです。
「えっ、そんなに違うの?」と驚かれるかもしれませんね。
実は、イタチは肉食動物。
だから、動物性のエサに強く引き寄せられるんです。
イタチが好むエサのランキングを見てみましょう。
- 生魚(特にイワシやサバ)
- 鶏肉(生や調理済み)
- 卵(生卵や茹でたもの)
- 小動物の肉(ネズミやウサギ)
- 果物(リンゴやバナナ)
具体的な数字を見てみましょう。
- 動物性エサ(魚や肉):捕獲成功率約75%
- 植物性エサ(果物):捕獲成功率約25%
動物性エサを使うと、植物性エサの3倍も捕獲率が上がるんです!
でも、ちょっと待ってください。
エサの鮮度も重要なポイントです。
新鮮なエサほど強い匂いを発し、イタチを引き寄せる効果が高くなります。
逆に、腐ったエサは避けましょう。
イタチが警戒して近づかなくなる可能性があります。
エサを罠に置く際のコツもあります。
- 小さく切って匂いを出しやすくする
- 罠の奥に置いてイタチを中に誘導する
- エサの周りに小麦粉を撒いて足跡を確認しやすくする
エサ選びは、まるで料理人がメニューを考えるように、イタチの好みを想像しながら選ぶのが楽しいですよ。
ただし、近所のペットを誤って捕獲してしまう可能性もあるので、ペットフードの使用は避けましょう。
イタチの好物で、かつ安全なエサを選ぶのがポイントです。
エサ選びを工夫して、イタチ捕獲の成功率をグッと上げちゃいましょう!
イタチの通り道に設置で「成功率5倍アップ」
イタチ捕獲の成功率を劇的に上げる方法があります。それは、イタチの通り道に罠を設置することです。
なんと、ランダムな場所に比べて成功率が5倍も高くなるんです。
「えっ、そんなに違うの?」と驚かれるかもしれませんね。
イタチは習慣的な動物で、毎日同じルートを通ることが多いんです。
この習性を利用すれば、捕獲の確率がぐんと上がります。
では、イタチの通り道をどうやって見つければいいのでしょうか。
ポイントは3つあります。
- 足跡を探す:イタチの足跡は小さな5本指が特徴的
- 糞を見つける:細長くねじれた形状のふんがある場所
- におい:イタチ特有のにおいがする場所
具体的な数字で見てみましょう。
- イタチの通り道に設置:捕獲成功率約75%
- ランダムな場所に設置:捕獲成功率約15%
通り道に設置すると、成功率が5倍にもなるんです!
でも、ちょっと待ってください。
通り道が見つかったからといって、そこにすぐに罠を置いてはいけません。
イタチは賢い動物なので、環境の変化に敏感なんです。
急に何か置かれていると警戒してしまいます。
そこで、罠の設置には段階を踏むのがコツです。
- まず、罠を置く場所に餌だけを置いてイタチを慣れさせる
- 数日後、罠を設置するが、まだ作動させない状態で餌を置く
- イタチが警戒せずに餌を食べるようになったら、罠を作動させる
イタチとの知恵比べ、結構楽しいものですよ。
通り道を見つけるのは、まるで探偵のような気分になれます。
足跡や糞を見つけたときの「あった!」という喜びは格別ですよ。
粘り強く探して、ぴったりの場所を見つけてくださいね。
イタチの通り道を発見できれば、捕獲成功率が5倍になる可能性が広がるんです。
がんばって、イタチ捕獲マスターを目指しましょう!
イタチ捕獲の意外な裏技と注意点

魚の缶詰の汁で「イタチを誘い込む」驚きの方法
イタチを捕獲するのに、魚の缶詰の汁が驚くほど効果的です。この意外な裏技で、イタチを罠に誘い込む確率がぐっと上がります。
「えっ、缶詰の汁?」と思われるかもしれませんね。
実は、イタチは魚の強い匂いに引き寄せられるんです。
特に、サバやイワシなどの青魚の缶詰がおすすめです。
使い方は簡単です。
罠の周りに缶詰の汁を少量ずつ撒いていきます。
まるで、イタチへの「においの道しるべ」を作るようなものです。
この匂いの道をたどって、イタチが罠まで誘われるというわけ。
ここで注意したいポイントがあります。
- 汁は少量ずつ。
たくさん撒きすぎると逆効果 - 罠の中にも少量の汁を入れる
- 新鮮な汁を使用。
古くなったものは避ける
確かに、その通りです。
そこで、こんな工夫をしてみてください。
小さな容器に汁を入れ、それを罠の近くに置くんです。
こうすれば、長時間匂いが持続します。
この方法のすごいところは、コストが安いこと。
高価な専用の誘引剤を買わなくても、家にある缶詰で十分なんです。
まさに、一石二鳥のアイデアですよね。
ただし、この方法を使う際は近所への配慮も忘れずに。
強い魚の匂いが苦手な方もいるかもしれません。
できるだけ人家から離れた場所で行うのがマナーです。
「よし、これで缶詰の汁作戦、試してみよう!」そんな気持ちになってきましたか?
イタチ捕獲の成功率アップに、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
古靴下でエサを包み「匂いを長持ち」させる技
イタチ捕獲の意外な裏技として、古い靴下を使ったエサの包み方があります。この方法で、エサの匂いを長持ちさせ、イタチを効果的に誘引できるんです。
「えっ、古靴下?」と驚かれるかもしれませんね。
でも、これがなかなかの優れものなんです。
古靴下には2つの大きな利点があります。
- エサの匂いを徐々に放出する
- エサが乾燥するのを防ぐ
まず、イタチの好物(生魚や鶏肉など)を小さく切ります。
それを古靴下に入れ、しっかり結びます。
この「エサ包み」を罠の中に吊るすんです。
この方法のポイントは、エサの匂いが長時間持続すること。
普通にエサを置くと、すぐに乾燥して匂いが弱くなってしまいます。
でも、靴下に包むことで、じわじわと匂いが漏れ出すんです。
まるで、イタチにとっての「香り袋」のようなものですね。
ここで、いくつかのコツをご紹介します。
- 靴下は洗濯したものを使う(人間の匂いを消すため)
- 綿100%の靴下が最適(合成繊維は匂いを通しにくい)
- 2〜3日ごとに新しいエサに交換する
大丈夫です。
靴下を罠にしっかり固定すれば問題ありません。
この方法の魅力は、身近なものを使えること。
わざわざ特別な道具を買わなくても、家にあるものでできちゃうんです。
エコでお財布にも優しい、まさに一石二鳥の技ですよ。
ただし、使用後の靴下の処理には注意が必要です。
生ゴミとして適切に捨てましょう。
そのまま放置すると、他の動物を引き寄せてしまう可能性があります。
「よし、古靴下でイタチ捕獲にチャレンジしてみよう!」そんな気持ちになってきましたか?
簡単で効果的なこの方法、ぜひ試してみてくださいね。
落ち葉で自然な環境作り「警戒心を解く」コツ
イタチ捕獲の成功率を上げる意外な方法として、落ち葉を使った自然な環境作りがあります。これで、イタチの警戒心を解き、罠に近づきやすくするんです。
「え?落ち葉を使うの?」と思われるかもしれませんね。
実は、イタチはとても警戒心の強い動物なんです。
人工的な罠をそのまま置いても、なかなか近づいてくれません。
そこで登場するのが、落ち葉です。
落ち葉を使った環境作りのポイントは3つあります。
- 罠の周りに落ち葉を敷き詰める
- 罠の上にも軽く落ち葉をかける
- 周辺の自然環境に合わせて落ち葉を配置する
まるで、罠に「自然のカモフラージュ」を施すようなものですね。
ここで、いくつかの注意点をご紹介します。
- 新鮮な落ち葉を使う(古いものは匂いで警戒されやすい)
- 罠の機能を妨げない程度に落ち葉を使う
- 定期的に落ち葉を交換する(湿って臭くなるため)
確かに少し手間はかかりますが、効果を考えれば十分に価値がありますよ。
近所の公園や自宅の庭で集めるのもいいですし、ホームセンターで園芸用の落ち葉を購入するのも一案です。
この方法の素晴らしいところは、自然に優しいこと。
化学物質を使わずに、自然の材料だけでイタチを誘引できるんです。
エコロジーな心を持つ方にもおすすめの方法ですね。
ただし、落ち葉を使う際は火災には十分注意してください。
特に、乾燥した季節は気をつけましょう。
また、使用後の落ち葉は適切に処分することも忘れずに。
「よし、落ち葉でイタチを誘おう!」そんな気持ちになってきましたか?
自然の力を借りたこの方法、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
イタチとの知恵比べ、意外と楽しいものですよ。
小麦粉で足跡を可視化!「最適な罠位置」の見つけ方
イタチ捕獲の成功率を dramatically に上げる方法として、小麦粉を使った足跡の可視化があります。これで、イタチの通り道を特定し、最適な罠の設置場所を見つけられるんです。
「えっ、小麦粉?」と驚かれるかもしれませんね。
実は、小麦粉はイタチの足跡を見つけるのに抜群の効果があるんです。
白い小麦粉の上に、イタチの小さな足跡がくっきり残るんです。
使い方は簡単です。
イタチが通りそうな場所に、薄く小麦粉を撒きます。
翌朝、その場所を確認すれば、イタチの足跡が見つかるはずです。
まるで、イタチの行動を追跡する探偵のようですね。
この方法のポイントは3つあります。
- 夕方に小麦粉を撒く(イタチは夜行性)
- 細長い帯状に撒く(広範囲をカバー)
- 天気予報をチェックする(雨だと流れてしまう)
イタチの通り道に罠を置くことで、捕獲の成功率がぐっと上がります。
ここで、いくつかの注意点をご紹介します。
- 小麦粉は薄く撒く(厚いと足跡が分かりにくい)
- 風の強い日は避ける(小麦粉が飛んでしまう)
- 使用後は掃除をする(放置すると虫が寄ってくる)
確かにその通りです。
だからこそ、使用は1晩限りにしましょう。
翌朝には必ず掃除をして、新しい小麦粉に交換することが大切です。
この方法の魅力は、コストが安いこと。
高価な機材を使わなくても、家にある小麦粉で十分なんです。
しかも、イタチに害を与えることもありません。
まさに、環境にも優しい方法ですね。
ただし、使用の際は近所への配慮も忘れずに。
風で小麦粉が飛んで、迷惑をかけないように注意しましょう。
また、食べ物を無駄にしているという印象を与えないよう、使用量は必要最小限に留めることが大切です。
「よし、小麦粉でイタチの足跡を追跡してみよう!」そんな気持ちになってきましたか?
この方法で、イタチの行動パターンを知り、効果的な罠の設置場所を見つけてくださいね。
イタチ捕獲の成功率アップに、きっと役立つはずです。
捕獲後の処置は「地域の条例」に要注意!
イタチを無事に捕獲できたら、次は適切な処置が重要です。ここで絶対に忘れてはいけないのが、地域の条例への注意です。
これを守らないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
「えっ、イタチの捕獲にも法律があるの?」と驚く方も多いでしょう。
実は、野生動物の捕獲や処置には、地域ごとに細かい規則が定められているんです。
これは、動物愛護の観点や生態系保護のためなんです。
地域の条例で定められていることには、主に次のようなものがあります。
- 捕獲の許可申請の必要性
- 捕獲可能な期間や場所の制限
- 捕獲後の処置方法(放獣や引き渡し先)
- 報告義務の有無
「知らなかった」では済まされないんです。
ここで、捕獲後の処置について一般的な注意点をいくつか紹介します。
- 捕獲から24時間以内に対処する
- 素手でイタチに触れない(ケガや感染症の危険あり)
- 遠くに放獣する場合は、元の生息地から5キロ以上離れた場所を選ぶ
- 放獣は自然豊かで、水源のある場所で行う
まずは、お住まいの市町村の公式ウェブサイトを確認してみてください。
そこで見つからない場合は、直接役所に問い合わせるのが確実です。
この手続きは少し面倒に感じるかもしれません。
でも、これをしっかり守ることで、イタチにも環境にも優しい対策ができるんです。
まさに、「人」と「自然」の共生を考えた処置といえますね。
条例を守ることで、思わぬメリットもあります。
例えば、適切な処置方法を教えてもらえたり、専門家のアドバイスを受けられたりすることもあります。
これは、イタチ対策の効果を高めるだけでなく、将来的な被害予防にもつながるんです。
「よし、しっかり条例を確認しよう!」そんな気持ちになってきましたか?
確かに少し手間はかかりますが、適切な処置は、イタチにとっても私たち人間にとっても、そして環境にとっても大切なことなんです。
イタチ捕獲後の処置、慎重に、そして適切に行いましょう。
それが、人と自然が共存する第一歩なんです。
がんばって、正しい方法でイタチ対策を進めてくださいね。