イタチの再侵入を防ぐには?【環境改善が重要】効果的な5つの予防策と注意点

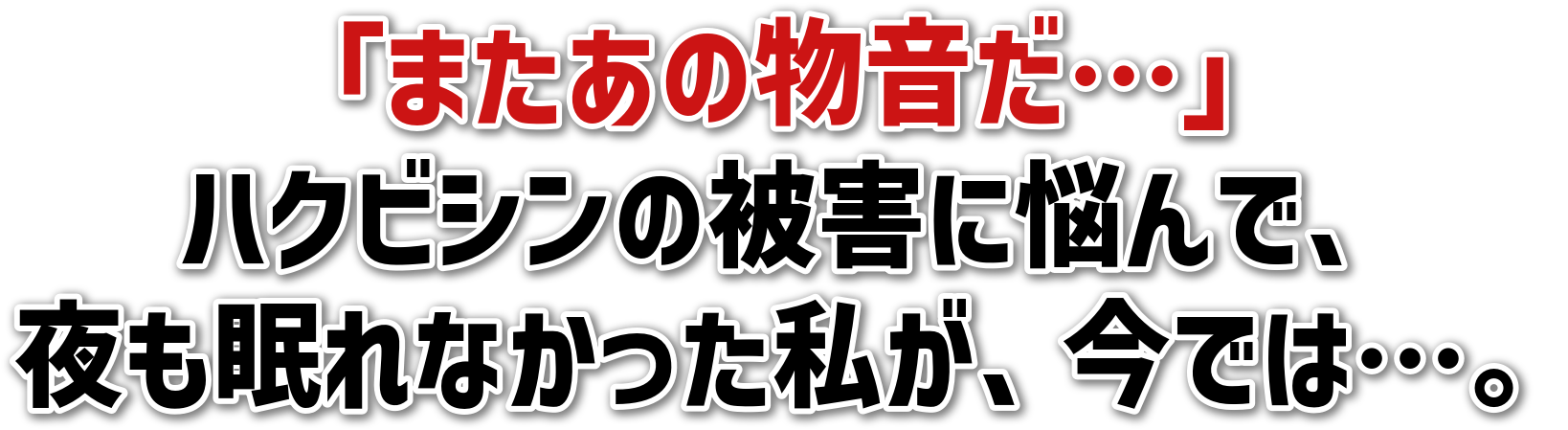
【この記事に書かれてあること】
イタチの再侵入に悩まされていませんか?- イタチの再侵入リスクは80%以上と非常に高い
- 環境改善がイタチの再侵入を防ぐ最も効果的な方法
- 物理的バリアと忌避剤の組み合わせが高い効果を発揮
- 定期的な監視が再侵入の早期発見と対策に不可欠
- 驚きの10の裏技でイタチを完全に寄せ付けない環境を作る
一度駆除したはずなのに、また姿を現すイタチ。
実はその再侵入リスクはなんと80%以上なんです!
でも、大丈夫。
適切な環境改善を行えば、イタチを寄せ付けない家づくりが可能です。
この記事では、イタチの再侵入を防ぐための効果的な方法を詳しく解説します。
「もうイタチには困らされたくない!」そんなあなたに、驚きの10の裏技も紹介。
イタチとの終わりなき戦いに、今日でピリオドを打ちましょう!
【もくじ】
イタチの再侵入がもたらすリスクと対策の重要性

イタチが再び家に侵入する可能性は「80%以上」!
イタチの再侵入リスクは驚くほど高いんです。なんと80%以上もの確率で、一度追い出したイタチが再び戻ってくる可能性があります。
「えっ、そんなに高いの?」と驚かれるかもしれませんね。
イタチは賢い動物で、一度居心地の良い場所を見つけると、そこを忘れません。
「ここは快適だったなぁ」とイタチの頭の中では記憶が残っているんです。
そのため、単に追い出すだけでは不十分なんです。
イタチが戻ってくる理由は主に3つあります。
- 餌が豊富にある
- 隠れ場所が多い
- 人間の気配が少ない
だからこそ、再侵入を防ぐには環境を根本から変える必要があるんです。
「でも、そんなに気をつけなくても大丈夫じゃない?」なんて思っていませんか?
実は、イタチの再侵入を放置すると、様々な問題が起きてしまうんです。
家の中がイタチだらけになっちゃうかもしれません。
そうならないためにも、再侵入リスクを十分に理解し、適切な対策を取ることが大切なんです。
再侵入を放置すると「家屋の損傷が加速」する危険性
イタチの再侵入を放っておくと、家にどんどん傷がついちゃうんです。「え、そんなに深刻なの?」と思われるかもしれませんが、実はかなり危険なんです。
イタチは家の中を自由に動き回るため、あちこちに傷をつけてしまいます。
特に注意が必要なのは次の3つの場所です。
- 屋根裏や天井
- 壁の中
- 床下
「ガリガリ…ガリガリ…」という音が聞こえてきたら要注意です。
特に怖いのが電線です。
イタチが電線をかじると、火災の危険まであるんです。
「えっ、火事になっちゃうの?」そうなんです。
だから本当に油断できません。
また、イタチの尿や糞も家を傷めます。
これらには酸性の成分が含まれているので、木材や金属をボロボロにしてしまうんです。
「うわぁ、想像しただけでゾッとする…」という感じですよね。
さらに、イタチが作る巣や通り道によって、断熱材が押しつぶされることもあります。
すると家の断熱効果が落ちて、冬は寒く夏は暑くなっちゃうんです。
こうした損傷が進むと、修理費用がどんどん膨らんでいきます。
最悪の場合、数十万円単位の出費になることも。
「そんなにお金かかっちゃうの!?」って感じですよね。
だからこそ、イタチの再侵入はすぐに対策を取ることが大切なんです。
家を守るためにも、早めの行動が鍵になります。
イタチの排泄物が引き起こす「衛生問題と健康被害」に注意
イタチが再び家に入り込むと、衛生面でも大問題なんです。特に気をつけなければいけないのが、イタチの排泄物です。
「え、そんなに危ないの?」と思われるかもしれませんが、実はかなり深刻なんです。
イタチの糞や尿には、いろいろな病原体が含まれています。
例えば:
- レプトスピラ菌
- サルモネラ菌
- 寄生虫の卵
「うわぁ、ゾッとする…」という感じですよね。
特に注意が必要なのが、イタチの尿です。
目に見えないので気づきにくいんです。
でも、イタチは歩き回りながらあちこちにおしっこをするんです。
「えっ、そんなところでも?」って驚くような場所にも、実はイタチの尿が…。
そして、イタチの排泄物から発生する強烈な臭いも問題です。
この臭いがすると、頭痛やめまい、吐き気を感じる人もいるんです。
「くさっ!」って思わず鼻をつまんでしまうかもしれません。
さらに、イタチの毛やフケもアレルギーの原因になることがあります。
「クシュン、クシュン」とくしゃみが止まらなくなったり、目がかゆくなったりするかもしれません。
こうした衛生問題は、家族全員の健康に影響を与える可能性があります。
特に子どもやお年寄り、持病のある人は注意が必要です。
だからこそ、イタチの再侵入を防ぐことが大切なんです。
家族の健康を守るためにも、早めの対策が重要になります。
「よし、しっかり対策しよう!」そんな気持ちになりますよね。
環境改善を怠ると「イタチの被害が悪化」する一方
環境改善をしないでいると、イタチの被害はどんどんひどくなっちゃうんです。「え、そんなに悪くなるの?」と思われるかもしれませんが、実はかなり深刻なんです。
まず、イタチの数が増えていきます。
イタチは年に2回、春と秋に子どもを産むんです。
1回の出産で3〜6匹の赤ちゃんが生まれるので、あっという間に大家族になっちゃいます。
「うわぁ、どんどん増えちゃう…」って感じですよね。
イタチの家族が増えると、次のような問題がどんどん大きくなります:
- 家の中の傷が増える
- 悪臭がひどくなる
- 夜中の騒音が増える
- 衛生状態が悪化する
一度人間の生活リズムを覚えてしまうと、より巧妙に行動するようになるんです。
「ぬかりないな…」って感心してしまうほどです。
例えば、人間が寝ている間だけ活動したり、音を立てずに動き回ったりするようになります。
そうなると、イタチがいることに気づくのが遅れてしまい、被害がどんどん大きくなっちゃうんです。
さらに、イタチが長期間住み着くと、家の価値まで下がってしまう可能性があります。
「えっ、そんなにひどいの?」って驚くかもしれませんが、本当なんです。
イタチの被害跡が残っていると、家を売るときや貸すときに不利になることがあるんです。
だからこそ、環境改善は早めに行うことが大切なんです。
イタチにとって「ここは住みにくいな」と思わせる環境を作ることで、被害の悪化を防ぐことができます。
「よし、今すぐ対策しよう!」そんな気持ちになりますよね。
単発の対策だけではダメ!「総合的なアプローチ」が必須
イタチ対策、ひとつだけやっても効果は薄いんです。「えっ、そうなの?」と驚かれるかもしれませんが、実は総合的に取り組むことが大切なんです。
イタチは賢い動物なので、単発の対策はすぐに見破られちゃうんです。
例えば、忌避剤を置いただけだと、イタチはすぐに「これは危なくないな」と気づいてしまいます。
「なんだ、大したことないじゃん」って感じでしょうか。
効果的なイタチ対策には、次のような方法を組み合わせる必要があります:
- 物理的なバリアの設置
- 忌避剤の使用
- 餌となるものの除去
- 隠れ場所の排除
- 定期的な監視と点検
また、対策を行う時期も重要です。
イタチの繁殖期である春と秋の前に、しっかりと準備をしておくことが大切です。
「よし、計画的に進めよう!」という感じですね。
さらに、家の中だけでなく、外周りの環境にも注意を払う必要があります。
庭や物置なども、イタチの隠れ家になる可能性があるんです。
「ここまで気をつけるの?」と思われるかもしれませんが、それくらい徹底的にやる必要があるんです。
そして、対策を一度やったらそれで終わり、というわけではありません。
定期的に効果を確認し、必要に応じて方法を変えたり、新しい対策を追加したりすることが大切です。
このように、イタチ対策は「総合的なアプローチ」が必須なんです。
一つひとつの対策を丁寧に、そして継続的に行うことで、イタチの再侵入を効果的に防ぐことができます。
「なるほど、やるべきことがはっきりしたぞ!」そんな気持ちになりますよね。
イタチの再侵入を防ぐための効果的な環境改善策

物理的バリアvsイタチの学習能力「どちらが勝つ?」
物理的バリアは効果的ですが、イタチの学習能力も侮れません。でも、適切に設置すれば、バリアの勝利です!
イタチってすごく賢い動物なんです。
「えっ、そんなに?」って思われるかもしれませんが、本当なんですよ。
迷路を30秒で攻略したり、新しい経路を3日で覚えたりするんです。
まるで小さな忍者のよう。
でも、賢いイタチにも弱点があります。
それは、物理的な障害物。
イタチは小さな体で隙間をすり抜けるのが得意ですが、しっかりとした物理的バリアには太刀打ちできないんです。
効果的な物理的バリアには、こんなものがあります:
- 金属製の網やシート
- 電気柵
- 超音波発生装置
特に注意したいのは、隙間をなくすこと。
イタチは5ミリメートルの隙間があれば入り込めるんです。
「えー!そんな小さな隙間から!?」って驚きますよね。
物理的バリアを設置する場所も重要です。
イタチが侵入しやすい場所、例えば屋根裏や換気口、配管周りなどを重点的に守りましょう。
「ここから入ってくるのか〜」って、イタチの目線で考えるのがコツです。
ただし、注意点があります。
イタチは学習能力が高いので、同じバリアを長期間使うと、突破される可能性があります。
だから、定期的にバリアの種類や配置を変えるのがおすすめ。
「よし、イタチ対策もアップデートだ!」って感じで楽しみながらやるといいですよ。
結局のところ、物理的バリアvsイタチの学習能力、どっちが勝つか?
答えは、適切に設置・管理された物理的バリアなんです。
頭がいいイタチも、しっかりしたバリアには勝てません。
がんばってイタチに勝ちましょう!
忌避剤の効果は「3か月」イタチの繁殖期と比較して
忌避剤は効果的ですが、3か月程度で効果が薄れます。イタチの繁殖期は年2回なので、タイミングよく使うのがポイントです。
「え?忌避剤ってそんなに効果が短いの?」って思われるかもしれませんね。
実は、忌避剤の効果持続期間は製品によって違いますが、一般的には1〜3か月程度なんです。
一方、イタチの繁殖期は年に2回、春と秋にやってきます。
つまり、忌避剤の効果が切れるタイミングと、イタチが活発になる時期がちょうど重なってしまうかもしれないんです。
「うわ、タイミング悪すぎ!」って感じですよね。
でも、大丈夫!
このタイミングを逆手にとって対策を立てましょう。
例えば:
- 春と秋の繁殖期前に忌避剤を新しく設置する
- 夏と冬に忌避剤の効果をチェックし、必要なら補充する
- 季節ごとに異なる種類の忌避剤を使い、イタチを油断させない
天然成分を使ったスプレータイプや、超音波を発する電子機器タイプなど。
「へぇ、選択肢が多いんだな」って思いますよね。
使い方のコツは、イタチの侵入経路や活動範囲に定期的に散布または設置すること。
「ここなら絶対通るはず!」というところを重点的に守りましょう。
また、忌避剤を使う時は、イタチの鼻の高さを意識するのもポイントです。
イタチの鼻は地面から約5センチの高さにあります。
「そんな低いところに?」って驚くかもしれませんが、ここに忌避剤の香りが届くように設置すると効果的なんです。
忘れてはいけないのが、定期的な効果確認と補充。
「もう大丈夫だろう」と油断すると、イタチにスキを与えちゃいます。
カレンダーにでも印をつけて、忘れずにチェックしましょう。
忌避剤とイタチの繁殖期、一見ミスマッチに見えるかもしれません。
でも、この知識を活かして賢く使えば、イタチの再侵入を効果的に防げるんです。
「よし、イタチに負けないぞ!」って気持ちで頑張りましょう!
餌となる小動物の駆除と「生態系への影響」を考える
餌となる小動物の駆除はイタチ対策に効果的ですが、生態系への影響も考える必要があります。バランスを取りながら対策を進めましょう。
「え?イタチの餌を無くせば来なくなるの?」って思われるかもしれませんね。
その通りなんです。
イタチが家に来る大きな理由の一つが、餌を求めてなんです。
イタチが好んで食べる小動物には、こんなものがあります:
- ネズミ
- モグラ
- 小鳥
- カエル
- 昆虫
「よし、全部退治しちゃおう!」って思うかもしれません。
でも、ちょっと待ってください。
小動物を全て駆除してしまうと、思わぬ影響が出る可能性があるんです。
例えば:
- 害虫が増える(小鳥や昆虫を食べる動物がいなくなるため)
- 土壌が悪くなる(モグラがいなくなって土が固くなる)
- 他の生き物の餌が減る(食物連鎖のバランスが崩れる)
生態系って、とてもデリケートなバランスで成り立っているんです。
じゃあ、どうすればいいの?
答えは、バランスを取ること。
完全に駆除するのではなく、数を減らす程度に留めるのがポイントです。
具体的には、こんな方法がおすすめです:
- 庭や家の周りを清潔に保つ(小動物の隠れ場所を減らす)
- 餌になりそうなものを放置しない(生ゴミや落ち葉など)
- 必要最小限の駆除を行う(完全駆除ではなく、個体数調整程度に)
「なるほど、そうすれば両立できるんだ!」って感じですよね。
餌となる小動物の駆除は、イタチ対策の重要な一歩です。
でも、自然界のバランスを大切にしながら進めることが大切。
「イタチも小動物も、みんなで上手に共存できるといいな」そんな気持ちで対策を進めていきましょう。
隠れ場所の除去と「イタチの生存本能」のせめぎ合い
イタチの隠れ場所を除去するのは効果的ですが、イタチの強い生存本能とのせめぎ合いになります。粘り強く対策を続けることが大切です。
「イタチって、どんなところに隠れるの?」って疑問に思いますよね。
実は、イタチはとっても器用で、ちょっとした隙間や暗がりを見つけては隠れ場所にしてしまうんです。
イタチがよく隠れる場所には、こんなところがあります:
- 屋根裏や天井裏
- 床下や壁の中
- 物置や倉庫の隅
- 積まれた薪や材木の間
- 庭の茂みや低木の下
イタチの体は細長くて柔軟なので、人間には想像もつかないような狭い場所にも入り込めるんです。
でも、こういった隠れ場所を全部なくしてしまえば、イタチは来なくなるんじゃないか?
そう思うかもしれません。
確かに、隠れ場所をなくすのは有効な対策の一つです。
ただし、そう簡単にはいきません。
なぜなら、イタチには強い生存本能があるからです。
「生きるためなら何でもする!」そんな感じで、新しい隠れ場所を必死で探すんです。
例えば、庭の茂みを刈り取ったら、今度は物置の隅に隠れるかもしれません。
物置を整理したら、今度は屋根裏に潜り込むかも。
「もう、いたちごっこだ!」って思ってしまいそうですよね。
じゃあ、どうすればいいの?
ポイントは、粘り強く続けることです。
イタチの生存本能は強いですが、人間の知恵と忍耐力はもっと強いんです。
具体的には、こんな対策を続けましょう:
- 定期的に庭や家の周りを点検し、新しい隠れ場所ができていないかチェックする
- 物を整理整頓し、イタチが隠れられそうな隙間をなくす
- 屋根や外壁の補修をこまめに行い、侵入口を塞ぐ
- 庭木の手入れを定期的に行い、茂みを作らない
「ふう、やっと追い払えた!」そんな日が来るはずです。
隠れ場所の除去とイタチの生存本能、一見すると終わりのない戦いに思えるかもしれません。
でも、諦めずに続けることで必ず効果は表れます。
「よし、イタチに負けないぞ!」そんな気持ちで頑張りましょう。
定期的な監視は「1週間に1回」が再侵入防止の鍵
定期的な監視は再侵入防止の要です。最初の1か月は週1回、その後は月1回のペースで行うのが効果的です。
「え?そんなに頻繁にチェックする必要があるの?」って思われるかもしれませんね。
でも、イタチ対策で大切なのは、早期発見・早期対応なんです。
イタチは、一度住み着くと繁殖して個体数が増えてしまいます。
そうなると対策も大変になっちゃうんです。
だから、再侵入のサインをいち早く見つけることが大切なんです。
では、具体的にどんなことをチェックすればいいのでしょうか?
ポイントは以下の3つです:
- 足跡や糞などの痕跡確認
- 物理的バリアや忌避剤の効果チェック
- 新しい侵入経路や隠れ場所のチェック
でも、慣れてくれば15分程度でサクッとできるようになりますよ。
特に注意したいのが、イタチの足跡と糞です。
イタチの足跡は5本指で、大きさは1〜2センチくらい。
糞は細長く捻じれた形で、長さは5〜8センチくらいです。
「うわ、具体的!」って思いますよね。
これらを見つけたら要注意です。
また、物理的バリアや忌避剤のチェックも大切です。
「あれ?この網に穴が開いてる!」「このスプレーの香りが薄くなってきたかも」なんて気づいたら、すぐに補修や交換をしましょう。
新しい侵入経路や隠れ場所のチェックも忘れずに。
イタチは賢いので、前回チェックした時にはなかった新しい場所を見つけるかもしれません。
「ここから入ってきたのか!」なんて驚くこともあるかもしれませんね。
監視の頻度は、最初の1か月は週1回がおすすめです。
その後は、状況を見て月1回程度に減らしていってもOKです。
「えっ、最初は毎週なの?」って思うかもしれませんが、初期のチェックが大切なんです。
もし監視中にイタチの痕跡を見つけたら、すぐに対策を立てましょう。
例えば:
- 侵入経路を特定し、塞ぐ
- 新しい忌避剤を設置する
- 周辺の環境を見直し、イタチを引き寄せる要因を取り除く
定期的な監視は、少し面倒に感じるかもしれません。
でも、これこそがイタチの再侵入を防ぐ鍵なんです。
「うちの家はイタチフリー!」そう胸を張って言えるよう、しっかりチェックを続けていきましょう。
イタチの再侵入を完全に防ぐ5つの驚きの裏技

コーヒーかすの「強烈な香り」でイタチを寄せ付けない!
コーヒーかすでイタチ撃退!?
意外ですが、とっても効果的なんです。
「えっ、コーヒーかすでイタチが寄ってこなくなるの?」って思いますよね。
実は、イタチは強い香りが苦手なんです。
特にコーヒーの香りは、イタチにとってはとても不快な匂いなんです。
使い方は簡単!
使い終わったコーヒーかすを乾燥させて、イタチが侵入しそうな場所にパラパラっと撒くだけ。
「これ、簡単すぎない?」って思うかもしれませんが、本当にこれだけなんです。
効果的な場所は、例えばこんなところ:
- 家の周りの地面
- 庭の植え込みの下
- 物置の入り口
- 換気口の周り
確かに雨で流されちゃうので、定期的に撒き直す必要があります。
でも、コーヒーを飲む度に新しいかすができるので、むしろ「エコだな〜」って感じですよね。
注意点はたった一つ。
コーヒーかすは湿気を吸いやすいんです。
湿ったままだと、カビが生えちゃう可能性があります。
「えー、それって逆効果じゃない?」って思いますよね。
だから、必ず乾燥させてから使うのがポイントです。
「よし、今日からコーヒーをたくさん飲もう!」なんて思っちゃいそうですが、飲みすぎには注意してくださいね。
イタチ対策と健康、両方大切ですからね。
コーヒーかすでイタチ撃退、意外だけど効果的。
しかも、コーヒーの香りで家の周りが良い匂いになるなんて、一石二鳥ですよね。
「これなら続けられそう!」って感じじゃないでしょうか。
ペットボトルの水の「反射光」がイタチを威嚇する仕組み
ペットボトルの水で、イタチを追い払える?実は、これがかなり効果的な方法なんです。
「えっ、ただのペットボトルでイタチが逃げるの?」って思いますよね。
実は、イタチは光の反射に敏感なんです。
特に、予期せぬ場所で光が反射すると、とても警戒するんです。
やり方はとっても簡単!
- 透明なペットボトルに水を入れる
- 庭や家の周りの日当たりの良い場所に置く
- それだけ!
でも、太陽光が水の入ったペットボトルに当たると、キラキラっと反射するんです。
この不規則な光の動きが、イタチにとっては「何か危険なものがいる!」って感じるシグナルになるんです。
特に効果的な場所は、こんなところ:
- 庭の入り口
- 花壇の周り
- 物置の前
- 家の周りの地面
確かに、夜は太陽光がないので効果は薄くなります。
でも、街灯や月明かりでも多少は反射するので、完全に無意味というわけではありません。
この方法のいいところは、お金がかからないことです。
「わー、これなら今すぐできる!」って感じじゃないですか?
ただし、注意点が一つ。
夏場は水が腐りやすいので、定期的に水を交換してくださいね。
「ちょっと面倒だな」と思うかもしれませんが、蚊の発生防止にもなるので一石二鳥です。
ペットボトルの水で、イタチを撃退。
エコで簡単、しかも効果的。
「よし、今日から始めてみよう!」そんな気分になりませんか?
家族みんなでペットボトル作戦、始めてみましょう!
アルミホイルの「音と光」でイタチを驚かせる方法
アルミホイルでイタチ対策?意外ですが、これがかなり効果的なんです。
「えっ、台所にあるあのアルミホイル?」って思いますよね。
そう、まさにアレなんです。
イタチは意外と臆病な動物で、予期せぬ音や光に敏感なんです。
アルミホイルには、イタチを驚かせる2つの効果があります:
- 風で揺れると「カサカサ」という音がする
- 光を反射してキラキラ光る
アルミホイルを30センチくらいの長さに切って、イタチが来そうな場所にぶら下げるだけ。
「へぇ、こんな簡単なの?」って驚くかもしれませんね。
特に効果的な場所は、こんなところです:
- 庭の木の枝
- フェンスの上
- 物置の入り口
- 換気口の周り
確かに、雨風に弱いので定期的に交換する必要があります。
でも、アルミホイルって安いですし、使い終わったら資源ゴミで出せるので、エコな対策法と言えますよね。
この方法の一番のポイントは、イタチの習性を利用していることです。
イタチは新しい環境の変化に敏感で、見慣れないものがあると警戒するんです。
「ふむふむ、イタチの気持ちを逆手に取るわけか」って納得ですよね。
ただし、注意点が一つ。
強風の日はアルミホイルが飛ばされる可能性があるので、しっかり固定してくださいね。
「そうか、ゴミにならないようにしないと」って気づきますよね。
アルミホイルでイタチ撃退、意外だけど効果的。
しかも、キラキラ光るアルミホイルで庭が少しオシャレになるかも?
「よし、今日からアルミホイル作戦、始めてみよう!」そんな気分になりませんか?
柔軟剤の香りで「イタチの嗅覚」を混乱させるテクニック
柔軟剤の香りでイタチを撃退?実は、これがかなり効果的な方法なんです。
「えっ、洗濯に使う柔軟剤のこと?」って思いますよね。
そうなんです。
イタチは嗅覚が非常に発達していて、強い香りが苦手なんです。
特に、人工的な香りは彼らにとってはとても不快なんです。
使い方は簡単!
こんな感じです:
- 古いタオルや布に柔軟剤を染み込ませる
- それをイタチが来そうな場所に置く
- 1週間ごとに香りを付け直す
特に効果的な場所は、こんなところです:
- 家の周りの地面
- 物置の入り口
- 庭の植え込みの下
- 換気口の近く
確かに、雨に濡れると効果が薄れてしまいます。
そんな時は、ペットボトルに柔軟剤を染み込ませた布を入れて、口を少し開けておくといいんです。
「なるほど、雨対策もバッチリだね」って感じですよね。
この方法の一番のポイントは、人間にとっては良い香りなのに、イタチにとっては不快な香りだということ。
「一石二鳥だね!」って思いませんか?
ただし、注意点が一つ。
香りが強すぎると、逆に人間が気分悪くなっちゃうかもしれません。
「そうか、やりすぎには注意だね」って気づきますよね。
適度な香りを保つのがコツです。
柔軟剤でイタチ撃退、意外だけど効果的。
しかも、家の周りが良い香りになるなんて素敵ですよね。
「よし、今日から柔軟剤作戦、始めてみよう!」そんな気分になりませんか?
家族みんなで協力して、イタチのいない快適な生活を目指しましょう!
風鈴の「予期せぬ音」でイタチを警戒させる戦略
風鈴の音でイタチを追い払う?意外ですが、これが実は効果的な方法なんです。
「えっ、あの夏の風物詩の風鈴?」って思いますよね。
そうなんです。
イタチは予期せぬ音に敏感で、特に金属音を嫌うんです。
風鈴のチリンチリンという音は、イタチにとってはとても不安を感じる音なんです。
使い方は本当に簡単!
こんな感じです:
- 風鈴を用意する(金属製がベスト)
- イタチが来そうな場所に吊るす
- 風に揺れるのを待つだけ
特に効果的な場所は、こんなところです:
- 庭の木の枝
- 軒下
- 物置の入り口
- ベランダ
確かにその通りです。
そんな時は、扇風機を使って風を起こすのもアリです。
「なるほど、人工的に風を作るわけか」って感じですね。
この方法の一番のポイントは、音が不規則に鳴ることです。
イタチは規則的な音にはすぐに慣れてしまいますが、風鈴の音は風の強さによって変わるので、慣れにくいんです。
「ふむふむ、イタチの習性を逆手に取るわけだ」って納得ですよね。
ただし、注意点が一つ。
夜中ずっと鳴っていると、近所迷惑になる可能性があります。
「そうか、人間のことも考えないとね」って気づきますよね。
夜は外すか、音が出にくいように工夫するのがいいでしょう。
風鈴でイタチ撃退、意外だけど効果的。
しかも、風鈴の音を聞いていると心が落ち着きますよね。
「よし、今日から風鈴作戦、始めてみよう!」そんな気分になりませんか?
イタチ対策をしながら、夏の風情も楽しめる。
一石二鳥の素敵な方法かもしれません。