イタチが床下に侵入する理由は?【暖かく隠れやすい環境】床下侵入を防ぐ4つの対策方法

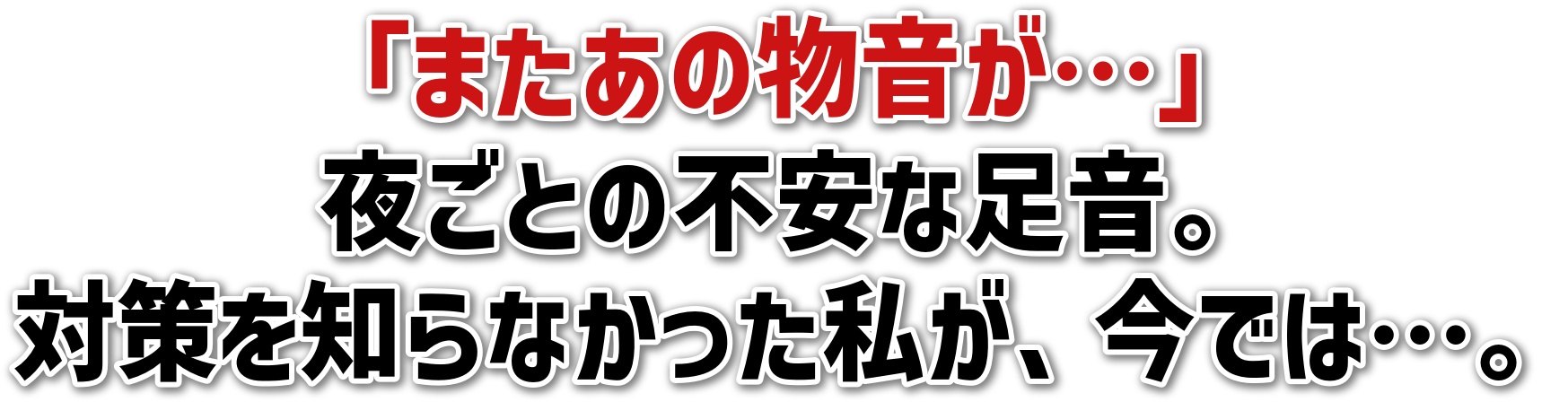
【この記事に書かれてあること】
イタチが床下に侵入して困っていませんか?- 床下はイタチの好む環境で侵入リスクが高い
- 季節による侵入傾向を理解し対策を立てる
- イタチの侵入による3つの深刻な被害を把握
- 侵入口の発見方法を目視と音で比較検討
- 5つの意外な対策法で効果的にイタチを撃退
実は、床下はイタチにとって理想的な住処なんです。
暖かくて隠れやすい環境が、イタチを引き寄せているんですね。
でも、大丈夫。
この記事では、イタチが床下に侵入する理由を詳しく解説し、さらに驚きの対策法を5つご紹介します。
「もうイタチには困らない!」そんな安心感を得られること間違いなしです。
イタチとの知恵比べ、一緒に始めてみましょう!
【もくじ】
イタチが床下に侵入する理由と深刻な被害

床下は「暖かく隠れやすい環境」でイタチの好物!
床下はイタチにとって理想的な住処なんです。暖かくて隠れやすい環境が、イタチを引き寄せてしまうのです。
イタチは体が細長く、小さな隙間をすいすい通り抜けられる特技を持っています。
そんなイタチにとって、床下は宝の山のような場所なんです。
「ここなら安心して暮らせそう!」とイタチは考えているんでしょうね。
床下がイタチに好まれる理由は主に3つあります。
- 温度が安定している
- 外敵から身を隠せる
- 食べ物が見つかりやすい
外の寒さや暑さから守られるので、体力を温度調節に使わなくて済むんです。
まるで高級ホテルのような快適さかもしれません。
隠れ場所としても最高です。
天井が低くて狭いので、大きな動物は入ってこられません。
イタチにとっては「ここなら安全」という安心感があるんです。
さらに、床下には小さな虫やネズミがいることも。
イタチにとっては絶好の食事処になってしまうんです。
「ごちそうさまです!」とイタチは喜んでいるかもしれませんね。
このように、床下はイタチにとって「暖かく隠れやすい環境」なので、どうしても侵入されやすくなってしまうのです。
イタチ対策には、この快適な環境を少し変えてあげることが大切になります。
イタチが床下を好む3つの理由「温度・隠れ場所・餌」
イタチが床下を好む理由は、「温度」「隠れ場所」「餌」の3つに絞られます。これらの要素が、イタチにとって魅力的な環境を作り出しているんです。
まず「温度」についてです。
床下は年中温度が安定しています。
夏は涼しく、冬は暖かい。
イタチにとっては、まるで高級リゾートホテルのような快適さなんです。
「ここなら季節を問わず過ごせるぞ」とイタチは考えているかもしれません。
次に「隠れ場所」です。
床下は天井が低く、狭い空間が広がっています。
大きな動物は入れませんが、細長いイタチにとっては理想的な隠れ家になるんです。
「ここなら誰にも見つからないぞ」とイタチは安心しきっているでしょう。
- 配管の周り
- 断熱材の隙間
- 柱の近く
体を丸めて休むのにぴったりなんです。
最後に「餌」です。
床下には小さな虫やネズミがいることがあります。
イタチにとっては、まるで24時間営業のレストランのようなものです。
「いつでも食事ができる!」とイタチは喜んでいるかもしれません。
これらの3つの要素が揃っているため、イタチは床下を理想的な生活の場として選んでしまうのです。
「ここなら快適に暮らせる」とイタチは考えているんでしょうね。
イタチ対策をする際は、これらの要素を少しずつ変えていくことが効果的です。
床下への侵入は「季節によって変化」冬と春に要注意!
イタチの床下侵入は季節によって変化します。特に冬と春には要注意なんです。
この時期、イタチは床下を特に魅力的な場所だと感じているんです。
まず冬です。
寒さが厳しくなると、イタチは暖かい場所を求めてやってきます。
「寒いよ〜」とイタチも思っているんでしょうね。
床下は外気から守られているので、イタチにとっては理想的な避難所になるんです。
- 外気温が下がり始める11月頃
- 寒さが最も厳しくなる1月〜2月
- まだ寒さが残る3月初旬
イタチの侵入が増える可能性が高いんです。
春になると、また別の理由で床下が魅力的になります。
この時期はイタチの繁殖期なんです。
「子育ての場所を探さなきゃ」とイタチも必死です。
床下は安全で暖かく、子育てに最適な環境なんです。
- 繁殖期が始まる4月頃
- 出産のピークを迎える5月〜6月
- 子育てが続く7月頃まで
イタチにとっては「ここなら安心して子育てができる」と感じる場所なんです。
夏と秋は比較的侵入が少なくなります。
でも油断は禁物です。
「涼しい場所を探そう」と思ったイタチが、夏でも床下に入ってくることがあるんです。
このように、イタチの床下侵入は季節によって変化します。
冬と春に特に注意を払い、年間を通じて対策を怠らないことが大切です。
イタチの生態を理解して、適切な時期に適切な対策を取ることが効果的なんです。
イタチの床下侵入で起こる「3つの深刻な被害」とは
イタチが床下に侵入すると、3つの深刻な被害が起こる可能性があります。これらの被害は、家の構造や住人の健康に影響を及ぼす可能性があるんです。
1つ目は「配線の噛み切り」です。
イタチは歯が鋭く、電気配線を噛み切ってしまうことがあるんです。
「これ、おもちゃかな?」とイタチは思っているかもしれません。
でも、これが原因で火災が起きる可能性があるんです。
ぞっとしますね。
2つ目は「断熱材の破壊」です。
イタチは巣作りのために断熱材を引き裂いてしまうことがあります。
「これで暖かい巣ができるぞ」とイタチは喜んでいるかもしれません。
でも、これによって家の断熱効果が落ち、光熱費が増加してしまうんです。
3つ目は「糞尿による悪臭や衛生問題」です。
イタチは床下で排泄をします。
「ここなら誰にも見つからないだろう」とイタチは考えているのかもしれません。
でも、これが原因で悪臭が発生したり、衛生状態が悪化したりするんです。
- 配線の噛み切り:火災のリスクが高まる
- 断熱材の破壊:光熱費の増加につながる
- 糞尿問題:悪臭や衛生状態の悪化を引き起こす
最初は小さな問題でも、放っておくと大きな問題に発展してしまうんです。
例えば、配線の噛み切りは最悪の場合、家屋全焼につながる可能性があります。
断熱材の破壊は、冬の寒さや夏の暑さをより厳しいものにしてしまいます。
糞尿問題は、家族の健康に悪影響を及ぼす可能性があるんです。
だからこそ、イタチの侵入にはできるだけ早く対処することが大切なんです。
被害が大きくなる前に、適切な対策を取ることが重要です。
イタチとの共存は難しいので、できるだけ早く退去してもらうことが賢明なんです。
イタチ対策で「殺虫剤散布はやっちゃダメ!」逆効果の理由
イタチ対策で殺虫剤を散布するのは、絶対にやってはいけません。これは逆効果になってしまうんです。
「殺虫剤なら効果がありそう」と思うかもしれませんが、実はそうではないんです。
まず、イタチは昆虫ではありません。
哺乳類なんです。
「虫を退治する薬」である殺虫剤は、イタチにはほとんど効果がないんです。
むしろ、イタチを苛立たせてしまう可能性があるんです。
- イタチは殺虫剤に耐性がある
- 殺虫剤の臭いでイタチが攻撃的になる可能性
- 殺虫剤が人や家畜に悪影響を与える
「何だこの臭いは!」とイタチも不快に思うでしょう。
ストレスを感じたイタチは、より攻撃的になったり、予期せぬ行動を取ったりする可能性があるんです。
さらに、殺虫剤は人や家畜の健康にも悪影響を与える可能性があります。
床下に散布した殺虫剤の成分が、家の中に漏れ出してくる可能性もあるんです。
「安全だと思っていたのに…」と後悔することになりかねません。
また、殺虫剤の使用は生態系にも悪影響を与えます。
イタチだけでなく、他の生き物にも影響を及ぼす可能性があるんです。
「一つの生き物を退治しただけ」のつもりが、思わぬ環境破壊につながってしまうかもしれません。
イタチ対策には、もっと安全で効果的な方法があります。
例えば、イタチの嫌がる匂いを利用したり、侵入経路を塞いだりする方法です。
これらの方法なら、イタチにも人にも優しい対策になるんです。
結局のところ、殺虫剤散布はイタチ対策として全く効果がなく、むしろ危険なんです。
「簡単に解決したい」という気持ちはわかりますが、安全で効果的な方法を選ぶことが大切です。
イタチと人間、両方に優しい対策を心がけましょう。
イタチの床下侵入を見抜く方法と対策の比較

「目視」vs「音」どちらが効果的?侵入口発見のコツ
イタチの侵入口発見には、目視と音の両方を組み合わせるのが最も効果的です。どちらも一長一短があるんです。
まず、目視での探し方から見てみましょう。
これは文字通り、目で見て探す方法です。
「ここから入ったのかな?」と思いながら、床下をじっくり観察するわけです。
目視の利点は、直接確認できること。
小さな穴や隙間、イタチの毛や足跡など、目に見える証拠を見つけやすいんです。
でも、欠点もあります。
床下の奥深くまで見通すのは難しいですし、暗くて見えにくい場所もあります。
一方、音での探し方はどうでしょうか。
これは、イタチの動きや鳴き声を聞き取って、侵入口を推測する方法です。
「カサカサ」「ガリガリ」といった音が聞こえたら、その付近に侵入口がある可能性が高いんです。
音の利点は、目で見えない場所でも探せること。
壁の中や床下の奥深くにいるイタチも、音で場所を特定できるんです。
でも、欠点もあります。
イタチが静かにしていると見つけられませんし、家の中の他の音と間違えてしまうこともあります。
- 目視の利点:直接確認できる、視覚的な証拠が残りやすい
- 目視の欠点:暗くて見えにくい場所がある、奥まで見通せない
- 音の利点:見えない場所でも探せる、動きを察知しやすい
- 音の欠点:イタチが静かだと見つけにくい、他の音と間違えやすい
例えば、まず音で大まかな場所を特定し、そのあと目視で詳しく調べる、といった具合です。
こうすれば、イタチの侵入口を見つける確率がぐっと上がりますよ。
昼と夜の侵入口調査「それぞれのメリット・デメリット」
イタチの侵入口調査は、昼と夜でそれぞれ特徴があります。どちらにもメリットとデメリットがあるんです。
まず、昼の調査から見てみましょう。
明るい時間帯なので、目視での確認がしやすいのが大きな利点です。
「あ、ここに小さな穴がある!」と気づきやすくなります。
昼の調査のメリットは他にもあります。
例えば、作業がしやすいこと。
足場も安定しますし、道具も使いやすいですよね。
また、イタチの足跡や毛、糞などの痕跡も見つけやすくなります。
でも、デメリットもあります。
イタチは夜行性なので、昼間はあまり活動しません。
そのため、動きを観察するのは難しいんです。
「本当にここから入ってるのかな?」と確信が持てないこともあります。
- 昼のメリット:明るくて見やすい、作業がしやすい、痕跡が見つけやすい
- 昼のデメリット:イタチの活動が少ない、動きの観察が難しい
イタチが活発に動き回る時間帯なので、その動きや音を観察しやすいのが大きな利点です。
「あ、あそこでカサカサ音がする!」と気づきやすくなります。
夜の調査のメリットは他にもあります。
例えば、イタチの鳴き声を聞きやすいこと。
また、暗闇の中で懐中電灯を使うと、イタチの目が光って見つけやすくなることもあります。
でも、デメリットもあります。
暗いので作業がしづらく、危険も伴います。
また、目視での細かい確認が難しくなります。
- 夜のメリット:イタチの活動が活発、音や動きの観察がしやすい
- 夜のデメリット:暗くて作業しづらい、細かい確認が難しい
昼は全体的な状況を確認し、夜はイタチの活動を観察する、といった具合です。
こうすれば、より確実にイタチの侵入口を見つけられるでしょう。
イタチの糞と尿「見た目と臭いの特徴」を徹底解説
イタチの糞と尿は、床下侵入の重要な手がかりです。見た目と臭いに特徴があるので、これらを知っておくと侵入の証拠を見つけやすくなります。
まず、イタチの糞について見てみましょう。
形は細長く、ねじれたような形をしています。
大きさは長さ5?8センチ、太さは鉛筆くらいです。
「あれ?細長いものがある」と思ったら、イタチの糞かもしれません。
色は黒っぽいものが多いですが、食べ物によって変わることもあります。
例えば、果物をたくさん食べていると赤っぽくなることも。
また、新鮮なものはツヤがあり、古くなると乾燥して色が薄くなります。
糞の中身をよく見ると、毛や骨、種などが混ざっていることがあります。
これはイタチの食生活を反映しているんです。
「ああ、こんなものを食べてるんだ」と、イタチの生態がわかりますね。
- 糞の特徴:細長くねじれた形、長さ5?8センチ、黒っぽい色
- 糞の内容物:毛、骨、種などが混ざることがある
これは見た目よりも臭いで気づくことが多いです。
イタチの尿には独特の強い臭いがあり、多くの人が「ムスク臭」と表現します。
「な、なんか変な臭いがする!」と思ったら要注意です。
尿の跡は、乾くと白っぽい斑点になります。
これは壁や床に付いていることが多いですね。
新鮮なものは湿っていて、触るとべたべたします。
臭いは時間が経つと強くなる傾向があります。
これは尿に含まれる物質が分解されるためです。
そのため、古い尿の跡ほど強烈な臭いを放つことになります。
- 尿の特徴:強いムスク臭、白っぽい斑点になる
- 臭いの変化:時間とともに強くなる傾向がある
「変な形の糞がある」「妙な臭いがする」と感じたら、イタチの可能性を疑ってみてください。
早期発見が対策の第一歩です。
プロの調査と自己調査「精度と費用対効果」の違い
イタチの侵入調査には、プロに依頼する方法と自分で行う方法があります。どちらにもメリットとデメリットがあるので、状況に応じて選ぶ必要があります。
まず、プロの調査の特徴を見てみましょう。
プロは専門知識と経験が豊富です。
「ここにイタチがいそうだな」と、素人には気づかないような小さな痕跡も見逃しません。
プロの調査の大きな利点は、高い精度です。
専門機器を使って、壁の中や床下の奥深くまで調べることができます。
例えば、熱を感知するカメラを使えば、イタチの居場所を特定しやすくなります。
また、プロならイタチの習性をよく知っているので、効率的に調査できます。
「この季節なら、ここに巣を作りやすい」といった予測も立てられるんです。
でも、デメリットもあります。
それは費用です。
プロの調査は決して安くありません。
「え、こんなにかかるの?」と驚く人も多いでしょう。
- プロ調査の利点:高い精度、専門機器の使用、効率的な調査
- プロ調査の欠点:高コスト
自分で行えば費用はかかりませんが、精度は下がります。
でも、工夫次第でそれなりの成果は上げられるんです。
自己調査の利点は、時間をかけてじっくり調べられること。
毎日少しずつ観察を続けられるので、イタチの行動パターンがわかりやすくなります。
また、自分の家のことは自分が一番よく知っています。
「この隙間、前はなかったよな」といった変化にも気づきやすいでしょう。
ただし、専門知識がないので見落としも多くなります。
「これって本当にイタチの痕跡なのかな?」と迷うこともあるでしょう。
- 自己調査の利点:低コスト、時間をかけて観察できる、家の状況に詳しい
- 自己調査の欠点:専門知識不足、見落としの可能性
軽度の侵入なら自己調査で十分かもしれません。
でも、深刻な被害が出ている場合や、自己調査で解決しない場合は、プロの力を借りるのも一つの手段です。
費用はかかりますが、確実な解決につながる可能性が高いですからね。
床下のイタチ被害「放置すると最悪の事態に」注意点
床下のイタチ被害を放置すると、思わぬ大事に発展する可能性があります。「まあ、しばらく様子を見よう」なんて悠長なことは言っていられません。
早めの対策が重要なんです。
まず、最も怖いのは火災のリスクです。
イタチは電線を噛み切ることがあります。
「これ、おもちゃかな?」とイタチは思っているのかもしれませんが、私たちにとっては大変危険な行動です。
噛み切られた電線がショートすると、火災の原因になりかねません。
次に心配なのは、家の構造への悪影響です。
イタチは断熱材を巣作りに使うことがあります。
「ふかふかして気持ちいい!」とイタチは喜んでいるかもしれませんが、これが進むと家の断熱性能が落ちてしまいます。
結果、冬は寒く、夏は暑くなり、光熱費もかさみます。
さらに、衛生面の問題も深刻です。
イタチの糞尿は強烈な臭いを放ちます。
「うわ、なんか臭い!」と感じたら、もうかなり進行しているかもしれません。
この臭いは簡単には消えず、家族の健康にも悪影響を与える可能性があります。
- 火災のリスク:電線を噛み切ることによる
- 構造への悪影響:断熱材の破壊、光熱費の増加
- 衛生面の問題:強烈な臭い、健康への悪影響
イタチ被害の跡が残っていると、家を売るときに大幅な値下げを求められる可能性があるんです。
「こんなはずじゃなかったのに…」と後悔しても後の祭り。
また、イタチが床下で繁殖すると、問題はさらに大きくなります。
子イタチが成長すると、被害の規模が急速に拡大します。
「かわいい子イタチ」も、私たちにとっては大きな脅威なんです。
心理的なストレスも見逃せません。
「今夜もイタチが来るかも…」と不安を感じ続けると、睡眠の質が落ちたり、日常生活に支障が出たりすることもあります。
こうした最悪の事態こうした最悪の事態を避けるためには、早めの対策が不可欠です。
イタチの痕跡を見つけたら、すぐに行動を起こしましょう。
侵入口を塞いだり、忌避剤を使ったりするなど、できることから始めるのがいいでしょう。
「まあ、大丈夫だろう」と安易に考えず、小さな兆候でも見逃さないことが大切です。
イタチ被害は時間とともに深刻化します。
早期発見、早期対策が、家族の安全と家の価値を守る鍵となるのです。
イタチの床下侵入を防ぐ5つの驚きの対策法

床下に「アルミホイルを敷き詰める」意外な効果とは
アルミホイルを床下に敷き詰めるという、意外な方法がイタチ対策に効果的なんです。「えっ、本当に?」と思われるかもしれませんが、実はこれ、結構すごい効果があるんですよ。
イタチは繊細な足裏を持っています。
アルミホイルの表面はザラザラしていて、イタチにとっては歩きにくいんです。
「うわ、この感触嫌だな」とイタチは思うでしょうね。
それに、アルミホイルはカサカサと音を立てます。
この音がイタチを怖がらせるんです。
使い方は簡単です。
床下に入れる場所に、アルミホイルを広げて敷き詰めるだけ。
イタチが通りそうな場所を重点的に覆いましょう。
- アルミホイルの光沢がイタチを驚かせる
- ザラザラした感触がイタチの足裏に不快感を与える
- 歩くと出るカサカサ音がイタチを怖がらせる
アルミホイルは破れやすいので、1ヶ月に1回くらいチェックして、必要に応じて交換しましょう。
また、床下が湿気やすい場合は、アルミホイルが錆びる可能性があります。
そういった場合は、防水加工されたアルミホイルを使うといいでしょう。
「でも、見た目が悪くないかな?」と心配する方もいるかもしれません。
でも大丈夫。
床下なので、普段は見えません。
それに、イタチ対策の効果を考えれば、少々見た目が気になっても十分価値があるはずです。
この方法、意外と効果的なんです。
「こんな簡単な方法でいいの?」と思うかもしれませんが、試してみる価値は十分にありますよ。
家にあるものでできる手軽なイタチ対策として、ぜひ活用してみてください。
「ペパーミントの香り」でイタチを寄せ付けない方法
ペパーミントの香りは、イタチを寄せ付けない強力な武器になります。「え?そんな身近なもので効果があるの?」と思われるかもしれませんが、実はこれ、すごく効果的なんです。
イタチは鼻が敏感で、強い香りが苦手です。
特にペパーミントの香りは、イタチにとってはとても不快なにおいなんです。
「うわ、この匂い嫌だな」とイタチは思うでしょうね。
使い方はいくつかあります。
まず、ペパーミントオイルを水で薄めて、スプレーボトルに入れます。
これを床下や侵入口周辺に吹きかけるんです。
また、ペパーミントティーバッグを床下の各所に吊るすのも効果的です。
- ペパーミントオイルを水で薄めてスプレーする
- ペパーミントティーバッグを床下に吊るす
- ペパーミントの植木鉢を床下の入り口付近に置く
香りは時間とともに薄くなるので、1週間に1回くらいのペースで新しくするといいでしょう。
また、ペパーミントの香りが強すぎると、人間も不快に感じる可能性があります。
適度な濃さに調整することが大切です。
「ちょっときつすぎるかな」と思ったら、水で薄めてみてください。
「でも、家中がペパーミントの香りになっちゃわないかな?」と心配する方もいるかもしれません。
でも大丈夫。
床下に使う分には、家の中にはそれほど香りは広がりません。
この方法、自然な香りを使うので、人にも環境にも優しいんです。
「化学薬品じゃなくて安心だな」と思える点も魅力的ですよね。
簡単で効果的なイタチ対策として、ぜひ試してみてください。
香り高い作戦で、イタチを撃退しましょう!
「超音波装置」でイタチを撃退!設置のポイント解説
超音波装置は、イタチを撃退する現代的な方法です。「音って本当に効くの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、これがなかなか効果的なんです。
イタチは私たち人間には聞こえない高周波の音に敏感です。
超音波装置は、イタチにとって不快な高周波音を発生させます。
「うわ、この音うるさい!」とイタチは思うでしょうね。
この音を嫌がって、イタチは別の場所に移動していくんです。
使い方は簡単です。
床下の入り口付近や、イタチが出没しそうな場所に装置を設置するだけ。
電源を入れれば、あとは装置が自動的に働いてくれます。
- 40キロヘルツ前後の周波数が最も効果的
- 床下の入り口付近に設置するのがおすすめ
- 複数台設置するとより効果的
ペットを飼っている場合は、ペットの様子を観察しながら使用しましょう。
また、壁や物に遮られると効果が弱まるので、なるべく開けた場所に設置することが大切です。
「ここなら音が通りやすいかな」と考えながら場所を選んでください。
電気代が気になる方もいるかもしれませんが、多くの超音波装置は省電力設計なので、そこまで心配する必要はありません。
「24時間つけっぱなしでも大丈夫かな」と安心して使えます。
この方法、目に見えない音でイタチを撃退できるのが魅力です。
「静かなのに効果があるなんてすごい!」と感心してしまいますよね。
現代技術を活用した効果的なイタチ対策として、ぜひ検討してみてください。
音波の力で、イタチとさよならしましょう!
床下周辺に「タバスコを撒く」驚きの効果と使い方
タバスコを床下周辺に撒くという、ちょっと変わった方法がイタチ対策に効果的なんです。「えっ、タバスコ?」と驚く方も多いでしょうが、これが意外と強力な武器になるんです。
イタチは辛いものが苦手です。
タバスコの辛さと強い香りは、イタチにとってはとても不快なんです。
「うわ、辛いよ!」とイタチは思うでしょうね。
この辛さと香りを嫌がって、イタチは別の場所に移動していくんです。
使い方は簡単です。
タバスコを水で薄めて、スプレーボトルに入れます。
これを床下の入り口や、イタチが通りそうな場所に吹きかけるんです。
- タバスコを水で5倍に薄める
- 床下の入り口周辺に重点的に撒く
- 週に1回程度の頻度で再度撒く
目立たない場所で試してから本格的に使用するといいでしょう。
また、タバスコの香りが強すぎると、人間も不快に感じる可能性があります。
「ちょっときつすぎるかな」と思ったら、さらに水で薄めてみてください。
「でも、家中がタバスコ臭くならない?」と心配する方もいるかもしれません。
でも大丈夫。
床下に使う分には、家の中にはそれほど香りは広がりません。
この方法、身近な調味料を使うので手軽にできるのが魅力です。
「家にあるもので対策できるなんて便利だな」と思えるはずです。
辛さと香りのダブルパンチで、イタチを撃退しましょう!
意外な使い方ですが、効果は抜群ですよ。
「コーヒーの出がらし」が持つイタチ撃退パワーとは
コーヒーの出がらしには、意外にもイタチを撃退するパワーがあるんです。「えっ、捨てるものなのに?」と思われるかもしれませんが、これがなかなか効果的な対策になるんです。
イタチは強い香りが苦手です。
コーヒーの出がらしの香りは、イタチにとってはとても不快なにおいなんです。
「うわ、この匂い嫌だな」とイタチは思うでしょうね。
この香りを嫌がって、イタチは別の場所に移動していくんです。
使い方は簡単です。
乾燥させたコーヒーの出がらしを、小さな布袋や網袋に入れます。
これを床下の入り口や、イタチが通りそうな場所に置くんです。
- コーヒーの出がらしをよく乾燥させる
- 小さな布袋や網袋に入れて設置
- 床下の入り口付近に重点的に置く
定期的にチェックして、カビが生えていたら新しいものに交換しましょう。
また、コーヒーの香りが強すぎると、人間も不快に感じる可能性があります。
「ちょっときつすぎるかな」と思ったら、設置する量を減らしてみてください。
「でも、家中がコーヒー臭くならない?」と心配する方もいるかもしれません。
でも大丈夫。
床下に使う分には、家の中にはそれほど香りは広がりません。
この方法、毎日飲むコーヒーの出がらしを再利用できるのが魅力です。
「ゴミを減らせて、イタチ対策もできるなんて一石二鳥だな」と思えるはずです。
エコでリーズナブル、そして効果的なイタチ対策として、ぜひ試してみてください。
コーヒーの香りで、イタチともさよならしましょう!