イタチ対策における地域協力のコツは?【情報共有が鍵】効果的な5つの取り組み方を紹介

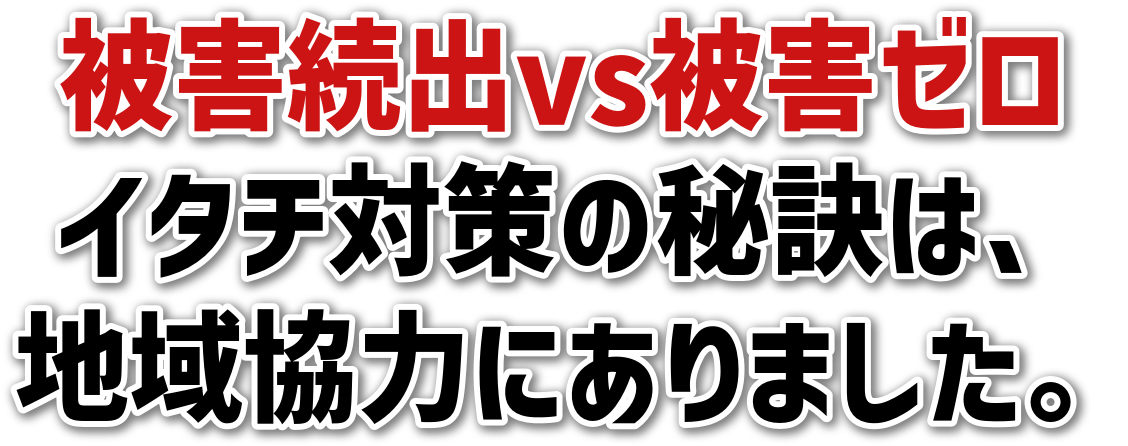
【この記事に書かれてあること】
イタチの被害に悩まされていませんか?- 情報共有によるイタチ被害の実態把握と対策立案
- 地域ぐるみの共同対策の立案と実施
- 教育・啓発活動を通じた地域意識の向上
- モニタリング体制の構築と「イタチマップ」の作成
- 地域協力と個人対策の効果とコストの比較
- 画期的な協力方法の導入(イタチウォッチング隊など)
個人での対策に限界を感じ、孤立感に苛まれている方も多いはず。
でも、大丈夫です!
地域ぐるみでの協力が、イタチ問題を解決する鍵なんです。
この記事では、情報共有から画期的な対策まで、5つの効果的な方法をご紹介します。
ご近所さんと力を合わせれば、イタチ被害を大幅に減らせるんです。
さあ、一緒に快適な暮らしを取り戻しましょう!
【もくじ】
イタチ対策における地域協力の重要性

情報共有が鍵!イタチ被害の実態を把握
イタチ対策では、地域全体での情報共有がとっても大切なんです。みんなで力を合わせれば、イタチの動きがよくわかるようになります。
まず、情報共有のコツをお伝えしましょう。
近所の人たちと「イタチ情報交換会」を開いてみるのはどうでしょうか。
「昨日、うちの庭でイタチを見たよ!」「実は、私の家の屋根裏から物音がするの」なんて具合に、みんなで気づいたことを話し合います。
どんな情報を共有すればいいのかというと、こんな感じです。
- イタチの目撃情報(日時や場所)
- 被害の状況(食べられた野菜、壊された物など)
- 効果があった対策方法
- イタチが侵入しそうな場所
「あれ?このあたりによく出没してるみたい」「この時間帯に活発みたいだね」なんてことがわかるんです。
情報共有の頻度は、月に1回くらいがちょうどいいでしょう。
でも、イタチが特に活発な春と秋には、週1回くらいのペースで情報交換するといいかもしれません。
「えー、そんなに頻繁に集まるの?面倒くさいなぁ」なんて思う人もいるかもしれません。
でも、コツコツと続けることで、イタチ対策の効果がグンと上がるんです。
みんなで力を合わせれば、イタチ退治もきっとうまくいきますよ。
共同対策の立案!5つのステップで効果的に
イタチ対策を地域ぐるみで行うなら、みんなで力を合わせて計画を立てるのが一番!5つのステップで効果的な共同対策を立ててみましょう。
まず、5つのステップをご紹介します。
- 現状把握:地域のイタチ被害の実態を調べる
- 目標設定:どこまで被害を減らしたいか決める
- 対策案の検討:みんなでアイデアを出し合う
- 役割分担:誰が何をするか決める
- 実施スケジュールの決定:いつまでに何をするか決める
まず、現状把握。
「うちの畑のトマトが食べられちゃった」「お隣の屋根裏からゴソゴソ音がするんだよね」なんて情報を集めます。
地図にシールを貼って、被害が多い場所を見える化するのもいいですね。
次に目標設定。
「半年で被害を半分に減らそう!」なんて具合に、具体的な数字を決めるのがポイントです。
対策案の検討では、みんなでワイワイとアイデアを出し合います。
「イタチが嫌いな匂いのハーブを植えてみては?」「ゴミ置き場を工夫してみよう」など、自由な発想で話し合いましょう。
役割分担では、得意分野を活かすのがコツ。
「私、植物に詳しいからハーブ担当やるよ」「僕、大工仕事得意だからゴミ置き場改造を担当するね」なんて感じで決めていきます。
最後に実施スケジュール。
カレンダーを見ながら「じゃあ、来月の第1週末からハーブを植え始めよう」「ゴミ置き場は再来月までに改造しよう」と決めていきます。
こうやって、みんなで話し合いながら計画を立てると、イタチ対策がぐっと身近に感じられるはず。
「よーし、みんなで頑張ろう!」という気持ちが高まり、効果的な対策につながるんです。
教育・啓発活動で地域の意識向上!3つの方法
イタチ対策を成功させるには、地域全体の意識を高めることが大切。効果的な教育・啓発活動で、みんなで楽しく学びながら対策を進めましょう。
おすすめの方法を3つご紹介します。
- イタチ博士による講習会
- 子供向け環境教育プログラム
- 地域イベントでの啓発ブース
専門家を招いて、イタチの生態や被害対策について学びます。
「えっ、イタチってそんなに賢いの?」「へぇ、こんな方法があったんだ」と、新しい発見がたくさんあるはずです。
質問コーナーを設けて、日頃の疑問をズバリ解決するのもいいですね。
次に、子供向け環境教育プログラム。
学校と連携して、総合学習の時間にイタチについて学ぶのはどうでしょう。
「イタチクイズ大会」や「イタチの巣づくり体験」など、楽しみながら学べる工夫をしましょう。
子供たちが家に帰って「ねぇねぇ、今日イタチのこと勉強したんだよ」と話せば、大人の関心も自然と高まります。
最後に、地域イベントでの啓発ブース。
お祭りや運動会など、人が集まる機会を利用しましょう。
「イタチとじゃんけん」ゲームや「イタチの足跡スタンプ」作りなど、遊び心満載の企画で楽しく学べます。
パネル展示で対策方法を紹介したり、相談コーナーを設けたりするのもいいですね。
これらの活動を定期的に行うことで、地域全体のイタチ対策への意識がグンと高まります。
「そういえば、最近イタチ見なくなったね」「うちの家庭菜園、被害が減ったわ」なんて声が聞こえてくるはず。
みんなで楽しく学びながら、イタチとの上手な付き合い方を見つけていきましょう。
「個人対策」は逆効果!地域で取り組む重要性
イタチ対策、一人で頑張っても効果は限定的。むしろ、逆効果になることも。
地域ぐるみで取り組むことが、本当に大切なんです。
個人対策の限界を見てみましょう。
例えば、Aさんが自分の家だけ強力な忌避剤を使ったとします。
確かに、Aさんの家からイタチは離れるでしょう。
でも、困ったイタチたちはどうするでしょうか。
そう、隣のBさんの家に移動してしまうんです。
「えー、うちにイタチが来るようになっちゃった!」とBさんが慌てふためく、なんてことになりかねません。
一方、地域全体で対策を講じると、こんなメリットがあります。
- イタチの生息域全体をコントロールできる
- 費用や労力を分散できる
- 多様なアイデアや知恵を結集できる
- 長期的な効果が期待できる
また、費用面でも「みんなで少しずつ負担すれば、個人でやるより安上がり」なんてこともあるんです。
さらに、地域で取り組むことで精神的な負担も軽減されます。
「私だけじゃない、みんなで頑張ってるんだ」という連帯感が生まれ、長続きする原動力になるんです。
もちろん、個人でできる対策もあります。
でも、それを地域全体の取り組みの一部として位置づけることが大切。
「私はこんな対策をしてるよ」「うちではこうしてるんだ」と情報交換しながら、みんなで力を合わせていく。
そんな姿勢が、イタチ対策成功の鍵になるんです。
地域ぐるみのイタチ対策!具体的な実践方法

モニタリング体制の構築!「イタチマップ」作成
イタチの動きを知るには、みんなで見守る体制が大切です。「イタチマップ」を作って、地域ぐるみでイタチの行動を把握しましょう。
まず、モニタリング体制の具体的な内容をご紹介します。
- イタチの目撃情報を記録する
- 被害状況を詳しく記録する
- 定期的なパトロールを実施する
- イタチの痕跡や新たな侵入経路を確認する
「へぇ、この辺りにイタチが多いんだね」「ここが侵入ポイントになってるみたい」と、イタチの行動パターンがよく分かるようになります。
では、誰がこの作業を担当するのでしょうか?
ボランティアを募って、当番制で実施するのがおすすめです。
「今週は山田さん宅周辺を見回りましょう」「来週は公園付近を重点的にチェックしてください」といった具合に、みんなで分担して行います。
そして、月に1回くらいのペースで報告会を開きましょう。
「先月はここで5回もイタチを見かけました」「この対策を始めてから、被害が半減しました」なんて情報を共有します。
みんなで知恵を出し合えば、より効果的な対策が見つかるはずです。
「えー、そんな面倒なことやってられないよ」なんて思う人もいるかもしれません。
でも、地域みんなで協力すれば、一人当たりの負担はグッと減ります。
それに、ご近所さんとのおしゃべりも楽しめるかも。
イタチ対策をきっかけに、地域の絆も深まるんです。
さあ、みんなでワイワイ楽しみながら、イタチマップを作ってみましょう!
地域協力vs個人対策!コスト面での比較
イタチ対策、地域で協力するのと個人でやるのとでは、どっちがお得なのでしょうか?結論から言うと、長い目で見れば地域協力の方がグンとお得なんです。
まず、短期的なコストを比べてみましょう。
- 個人対策:忌避剤や防護ネットなどを自腹で購入
- 地域協力:費用を皆で分担し、一人当たりの負担は少なめ
「うちだけ守れればいいや」と思って、数千円の忌避剤を買うだけで済ませる人もいるでしょう。
でも、長期的に見るとどうでしょう?
- 個人対策:効果が薄れるたびに新しい対策が必要
- 地域協力:一度体制を整えれば、継続的に効果を発揮
「あれ?また来ちゃった」「今度は違う対策品を買わなきゃ」の繰り返し。
結局、長い目で見ると高くつくんです。
一方、地域協力なら初期投資は少し高くても、その後のコストはグッと抑えられます。
例えば、地域全体でフェンスを設置したり、イタチの好まない植物を植えたりする。
一度やってしまえば、その効果は長く続きます。
それに、意外な節約効果も。
「お隣さんが効果的な対策を見つけたよ」「じゃあ、うちもそれを真似してみよう」といった情報共有で、無駄な出費を避けられるんです。
「でも、お金を出し合うのは気が引けるな」なんて思う人もいるかも。
そんな時は、物やスキルの提供でも協力できます。
「私、大工仕事得意だから、フェンス作りを手伝うよ」「うちの庭の植物を分けてあげるね」なんて具合に。
みんなで知恵とリソースを出し合えば、個人対策よりもずっとお得に、そして効果的にイタチ対策ができるんです。
さあ、近所の人と相談して、賢く経済的なイタチ対策を始めてみませんか?
地域協力vs個人対策!手間と効果の違い
イタチ対策、一人でコツコツやるのと、みんなで協力するのとでは、手間と効果に大きな違いがあります。結論から言うと、地域協力の方が長期的には手間が少なく、効果も高いんです。
まずは、手間の比較から見てみましょう。
- 個人対策:毎日の見回りや対策グッズの設置・管理が必要
- 地域協力:役割分担で一人当たりの負担が減少
まるで、いたちごっこ...じゃなくて、イタチとのいたちごっこですね。
一方、地域協力なら「今週の見回りは田中さんの担当だから、うちは来週でいいや」なんて具合に、負担を分散できます。
初期段階では話し合いや体制作りで少し手間がかかりますが、軌道に乗れば個人対策よりもずっとラクチンです。
次に、効果の違いを見てみましょう。
- 個人対策:一時的な効果はあるが、イタチが別の場所に移動するだけ
- 地域協力:広範囲で一斉に対策を行うため、長期的な効果が期待できる
「えー、うちに来るようになっちゃった」と隣の人が困ることになります。
でも、地域協力なら違います。
みんなで一斉に対策を行えば、イタチにとって「この地域には住みにくいな」と感じさせることができます。
長期的に見れば、イタチの生息域そのものを変えることも可能なんです。
「でも、みんなと協力するのって面倒くさそう...」なんて思う人もいるかもしれません。
確かに最初は大変かもしれません。
でも、慣れてくれば「今度のイタチ対策会議で、近所の人とおしゃべりできるの楽しみだな」なんて思えるようになるかも。
イタチ対策をきっかけに、地域のつながりが深まる。
そんな素敵な副産物も期待できるんです。
さあ、みんなで力を合わせて、楽しみながらイタチ対策を進めてみませんか?
協力体制vs単独行動!精神的負担の軽減効果
イタチ対策、一人で悩むより、みんなで協力した方が心が軽くなります。なぜなら、協力体制には精神的負担を軽くする大きな効果があるんです。
まず、単独行動の場合を考えてみましょう。
- 「またイタチが来た...」と一人で悩む
- 対策がうまくいかず、自己嫌悪に陥る
- 近所迷惑を心配して、誰にも相談できない
「もう、イタチなんてどうでもいい!」なんて投げ出したくなっちゃいますよね。
一方、協力体制ではどうでしょうか。
- 悩みを共有し、心強さを感じられる
- 成功体験を分かち合い、モチベーションが上がる
- 役割分担で、一人当たりの責任感が軽減される
例えば、イタチ対策の情報交換会を開いてみましょう。
「うちではこんな方法が効果あったよ」「へぇ、それいいね。うちでも試してみよう」なんて会話が弾みます。
失敗談を話し合って、みんなで笑い飛ばすこともできます。
「あはは、うちのイタチ、忌避剤の匂いを嗅いでから、よけいに庭に来るようになっちゃったよ」なんて具合に。
また、協力体制があれば、休息も取りやすくなります。
「今週はちょっと忙しいから、イタチ見回りは佐藤さんにお願いしよう」なんて具合に、負担を分散できるんです。
そして、何より大切なのが連帯感。
「私たちの地域は、私たちで守る!」そんな思いが芽生えると、イタチ対策が単なる面倒な作業から、地域みんなの絆を深める素敵な活動に変わるんです。
「えー、そんな面倒なことやりたくないな」なんて思う人もいるかもしれません。
でも、一度試してみると意外と楽しいかも。
イタチ対策をきっかけに、新しい友達ができるかもしれません。
さあ、勇気を出して、ご近所さんに声をかけてみましょう。
きっと、心強い味方が見つかるはずです。
情報共有vs孤立!対策成功率の違い
イタチ対策、情報を共有するのと一人で孤立するのとでは、成功率に雲泥の差があります。結論から言うと、情報共有をする方が圧倒的に成功率が高いんです。
まず、孤立して対策を行う場合のデメリットを見てみましょう。
- 限られた情報や経験しか活用できない
- 効果的な対策を見逃す可能性が高い
- イタチの行動パターンを把握しきれない
一方、情報共有を行う場合はどうでしょうか。
- 多様な経験と知識を集められる
- 効果的な対策をすぐに広められる
- イタチの行動を広範囲で把握できる
例えば、イタチ対策の成功事例を共有する会を開いてみましょう。
「うちでは、庭にラベンダーを植えたらイタチが来なくなったよ」「へぇ、それいいね。私も試してみよう」なんて具合に、成功体験がどんどん広がっていきます。
また、イタチの目撃情報を地図にまとめると、行動パターンが見えてきます。
「この道をよく通るみたいだね」「じゃあ、ここに重点的に対策を施そう」と、効率的な対策が可能になるんです。
そして、失敗情報の共有も大切です。
「この方法は効果なかったから、みんな気をつけてね」なんて情報があれば、無駄な努力や出費を避けられます。
「でも、私の失敗談なんて恥ずかしくて言えないよ...」なんて思う人もいるかもしれません。
でも大丈夫。
みんな同じように悩んでいるんです。
むしろ、あなたの経験が誰かの役に立つかもしれません。
情報共有は、イタチ対策の成功率を大きく高めるだけでなく、地域の絆も深めてくれます。
「イタチ情報、今日も0件だって。みんなの努力が実を結んでるね!」なんて会話が聞こえてくる日も、そう遠くないはずです。
さあ、勇気を出して、ご近所さんと情報交換を始めてみましょう。
きっと、予想以上の成果が待っていますよ。
きっと、予想以上の成果が待っていますよ。
イタチ対策の情報共有、実は楽しみながらできるんです。
例えば、「イタチ目撃情報掲示板」を作ってみるのはどうでしょう。
ご近所さんと協力して、イタチの出没情報や効果的だった対策をメモ書きで貼り付けていきます。
「昨日の夜9時頃、公園でイタチを見かけました」「うちの庭に植えたミントの匂いで、イタチが寄り付かなくなりました」なんて具合に。
この掲示板を見るのが日課になれば、自然と情報共有が習慣化します。
「今日はどんな情報があるかな?」とワクワクしながら見に行く人も出てくるかもしれません。
また、「イタチ対策成功事例コンテスト」なんてイベントを開催するのも面白いかもしれません。
みんなで知恵を絞った対策方法を発表し合い、一番効果的だった方法を表彰します。
「へぇ、そんな方法があったんだ!」「これ、うちでも使えそう」と、新しいアイデアがどんどん生まれるはずです。
このように、楽しみながら情報を共有することで、イタチ対策の成功率はグンと上がります。
同時に、地域のつながりも深まり、「イタチ問題をきっかけに、ご近所さんと仲良くなれた」なんて嬉しい副産物も。
さあ、今すぐご近所さんに声をかけてみましょう。
「イタチ対策、一緒に頑張りませんか?」きっと、予想以上の反響があるはずです。
みんなで力を合わせれば、イタチ問題なんてあっという間に解決できるかもしれません。
そして、その先には、イタチとも共存できる、笑顔あふれる地域の未来が待っているんです。
イタチ対策における地域協力の画期的な方法

「イタチウォッチング隊」結成!子供たちの力を活用
子供たちの好奇心と行動力を活かした「イタチウォッチング隊」の結成が、イタチ対策に新しい風を吹き込みます。「え?子供たちにイタチ対策?」と思う方もいるかもしれません。
でも、これが意外と効果的なんです。
子供たちの鋭い観察力と純粋な探究心が、大人には気づかないイタチの行動パターンを見つけ出すかもしれません。
まず、「イタチウォッチング隊」の活動内容を見てみましょう。
- 定期的なパトロールで、イタチの目撃情報を集める
- イタチの足跡や糞などの痕跡を探す
- 見つけた情報を地図にまとめる
- 大人たちに報告会を開く
「わぁ、イタチの足跡見つけた!」「ここにフンがあるよ!」なんて声が聞こえてきそうですね。
さらに、この活動には隠れた効果もあるんです。
子供たちが熱心に活動する姿を見て、大人たちも刺激を受けます。
「子供たちがこんなに頑張ってるんだから、私たちも何かしなきゃ」と、地域全体の意識が高まるんです。
ただし、安全面には十分な配慮が必要です。
大人の付き添いを必須にしたり、活動エリアを限定したりするなど、ルールづくりも大切です。
「イタチウォッチング隊」の活動を通じて、子供たちは自然観察の楽しさを知り、地域への愛着も深まります。
将来の環境保護活動家が、ここから生まれるかもしれません。
さあ、子供たちの力を借りて、楽しみながらイタチ対策を進めましょう!
「イタチ対策アドバイザー」任命!シニアの知恵を結集
地域のシニア層を「イタチ対策アドバイザー」として任命することで、長年の経験と知恵を活かした効果的なイタチ対策が可能になります。「えっ、おじいちゃんやおばあちゃんにイタチ対策?」と思う人もいるかもしれません。
でも、シニアの方々の豊富な生活経験は、イタチ対策にとって貴重な宝物なんです。
まず、シニアの方々がイタチ対策アドバイザーとして活躍できる理由を見てみましょう。
- 長年の庭いじりで培った植物の知識
- 昔ながらの知恵や工夫を知っている
- 地域の歴史や環境の変化を熟知している
- 時間に余裕があり、細やかな観察が可能
シニアの方々の役割はこんな感じです。
- 定期的な「イタチ対策会議」での助言
- 若い世代への知識伝授
- 地域の環境変化の記録と分析
- 伝統的な対策方法の再評価と提案
「まだまだ私たちにも役割があるんだね」「若い人たちの役に立てて嬉しいわ」なんて声が聞こえてきそうです。
さらに、この取り組みには素敵な副産物も。
世代を超えた交流が生まれ、地域のきずなが深まるんです。
子供たちが「イタチ博士のおじいちゃん」を慕って訪ねてくるなんて光景も見られるかもしれません。
イタチ対策を通じて、シニアの方々の豊かな経験と知恵を地域に還元する。
そんな素敵な取り組みを、ぜひ始めてみませんか?
きっと、イタチ対策だけでなく、地域全体が明るく活気づくはずです。
空き家活用作戦!「イタチ一時生息地」として管理
空き家をイタチの一時的な生息地として活用する方法が、新たなイタチ対策として注目を集めています。一見奇抜に思えるこの方法、実は画期的な効果があるんです。
「えっ、わざわざイタチを呼び寄せるの?」と驚く方もいるでしょう。
でも、これには深い理由があるんです。
まず、この方法のメリットを見てみましょう。
- イタチの行動を予測しやすくなる
- 住宅地への侵入を減らせる
- 計画的な管理が可能になる
- 空き家の有効活用になる
- 安全性を確認した空き家を選ぶ
- イタチが好む環境を整える(隠れ場所や水場の確保)
- 定期的な見回りと清掃を行う
- イタチの行動を観察し、記録する
ただし、この方法には慎重な対応が必要です。
近隣住民への十分な説明と同意を得ることが大切です。
「イタチを誘致するなんて、危険じゃないの?」という不安の声にも、丁寧に答えていく必要があります。
また、定期的な管理と観察が欠かせません。
「今週のイタチウォッチ、私の番ね」「イタチマップの更新、忘れずにしなきゃ」なんて会話が、地域で飛び交うかもしれません。
この方法を通じて、イタチとの共生の道が見えてくるかもしれません。
自然との調和を図りながら、人間の生活も守る。
そんなバランスの取れた対策が、この空き家活用から生まれる可能性があるんです。
イタチ対策を通じて、地域の課題である空き家問題にも一石を投じる。
そんな一石二鳥の取り組み、挑戦してみる価値はありそうですね。
地域イベントで盛り上がる!「イタチクイズ大会」開催
イタチ対策を楽しく学ぶ「イタチクイズ大会」の開催が、地域の一体感を高める新しい方法として注目されています。知識を競い合いながら、みんなでイタチ対策への理解を深めていくんです。
「え?イタチのクイズって面白いの?」と思う人もいるかもしれません。
でも、これが意外と盛り上がるんです。
イタチクイズ大会の魅力を見てみましょう。
- 楽しみながらイタチの知識が身につく
- 世代を超えた交流の場になる
- 地域全体の意識向上につながる
- イタチ対策のアイデアが生まれる可能性がある
- 地域の公民館や学校の体育館を会場に選ぶ
- 年齢別のチーム戦で競い合う
- 〇×クイズやイラスト問題など、バラエティに富んだ出題形式にする
- 優勝チームには「イタチ博士認定証」を贈呈
クイズの内容は、イタチの生態から対策方法まで幅広く。
例えば、「イタチの好きな食べ物は?」「イタチが嫌う匂いは?」「イタチの足跡の特徴は?」など、実用的な知識を問う問題を出題します。
さらに、クイズ大会の後には、参加者同士で意見交換会を開くのもいいでしょう。
「あの問題、意外だったね」「こんな対策を思いついたんだけど、どう思う?」なんて会話が飛び交えば、新たなアイデアが生まれるかもしれません。
この「イタチクイズ大会」を通じて、地域全体がイタチ対策に興味を持ち、積極的に取り組む雰囲気が生まれます。
知識を楽しく身につけながら、地域の絆も深まる。
そんな一石二鳥の取り組み、ぜひ挑戦してみませんか?
スマホアプリで情報共有!「リアルタイムイタチ情報」
地域専用のスマホアプリ「リアルタイムイタチ情報」の開発が、イタチ対策の新たな一手として注目を集めています。最新技術を活用して、みんなで手軽に情報を共有する。
そんな画期的な方法なんです。
「えっ、イタチのためにアプリ?」と驚く方もいるでしょう。
でも、これが意外と効果的なんです。
まず、このアプリの主な機能を見てみましょう。
- イタチの目撃情報をリアルタイムで投稿・共有
- 地図上でイタチの出没地点を可視化
- 効果的だった対策方法の投稿機能
- イタチ被害の通報と対応状況の確認
- イタチに関する豆知識のプッシュ通知
イタチを見かけたら、すぐにアプリを開いて場所と時間を投稿。
「今、公園でイタチを見ました!」「裏庭に侵入の形跡あり」なんて具合に、リアルタイムで情報が共有されます。
このアプリのメリットは大きいんです。
- 素早い情報共有で、迅速な対策が可能に
- イタチの行動パターンが見えやすくなる
- 対策の効果を皆で確認できる
- 地域全体の意識向上につながる
ただし、個人情報の取り扱いには十分注意が必要です。
利用規約をしっかり設け、情報の悪用を防ぐ工夫も欠かせません。
また、アプリの使い方講習会を開くのもいいでしょう。
「おじいちゃん、ここをタップするんだよ」「あら、私でも簡単に使えるわね」なんてやり取りが、世代を超えた交流のきっかけになるかもしれません。
このアプリを通じて、地域全体がイタチ対策に一丸となって取り組む。
そんな一体感が生まれるんです。
最新技術を味方につけて、みんなで楽しくイタチ対策。
そんな新しい形の地域協力、始めてみませんか?